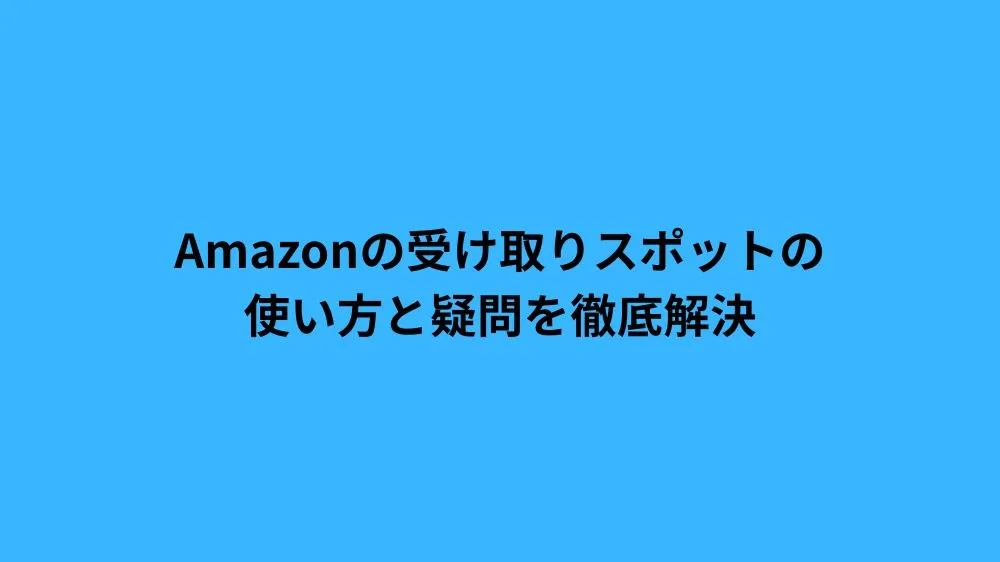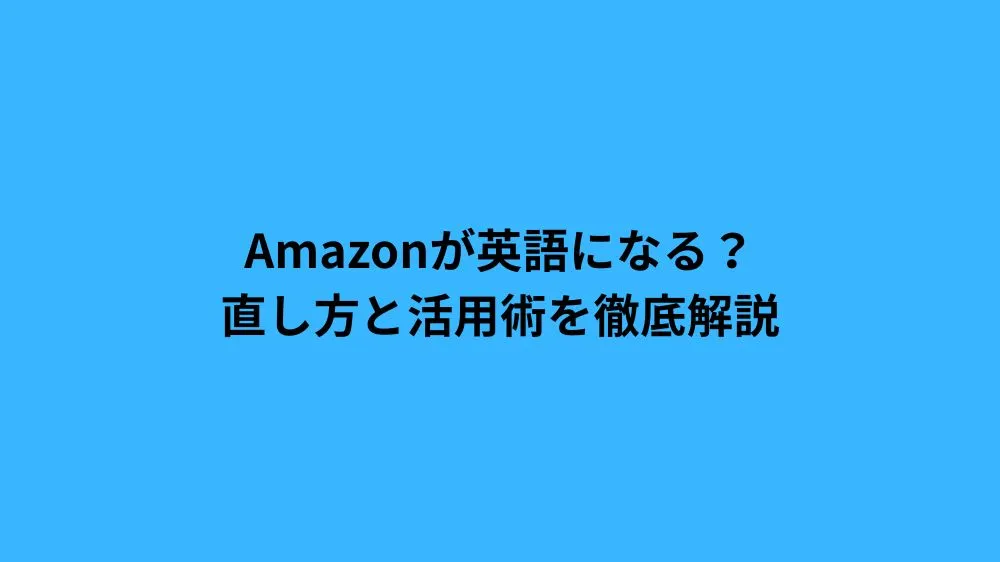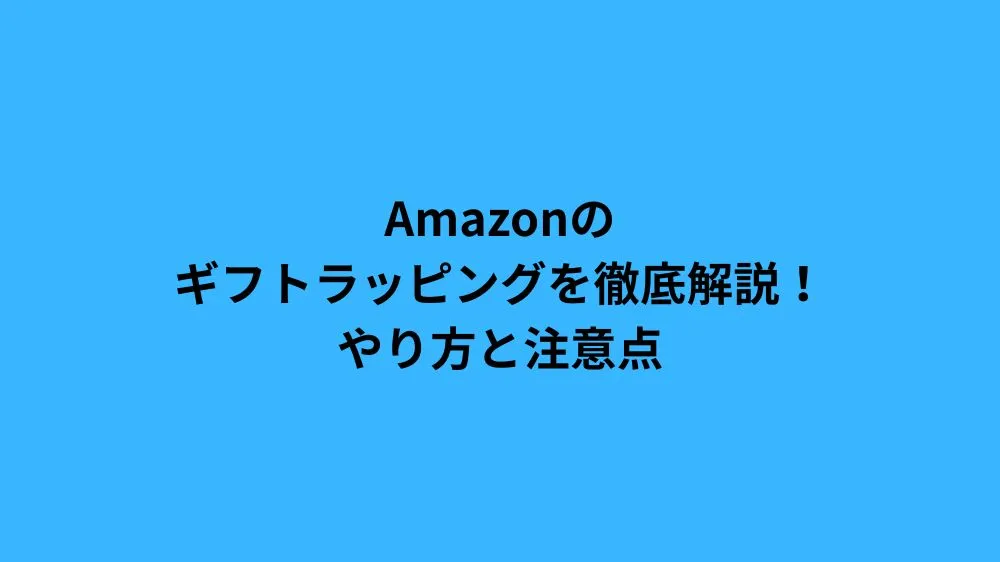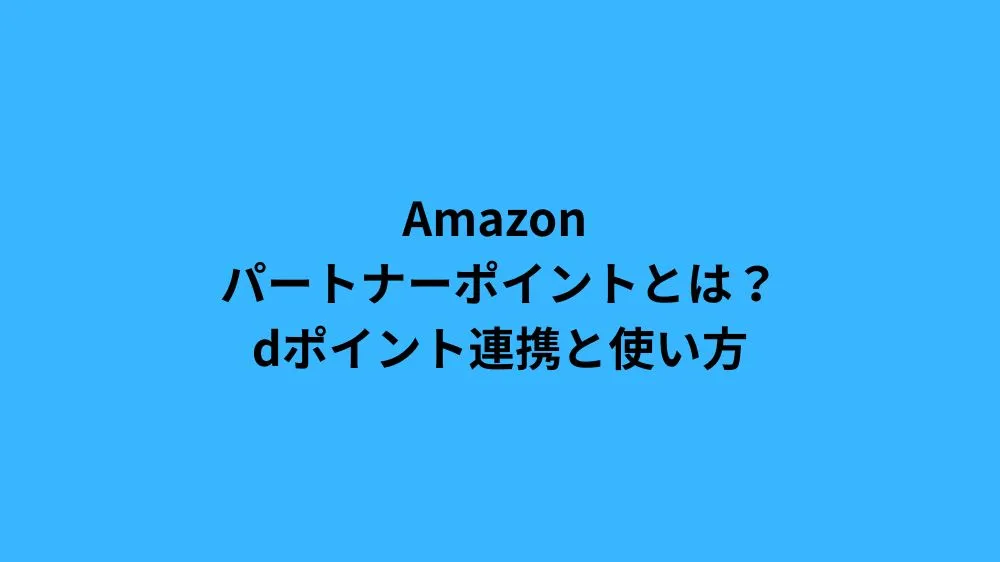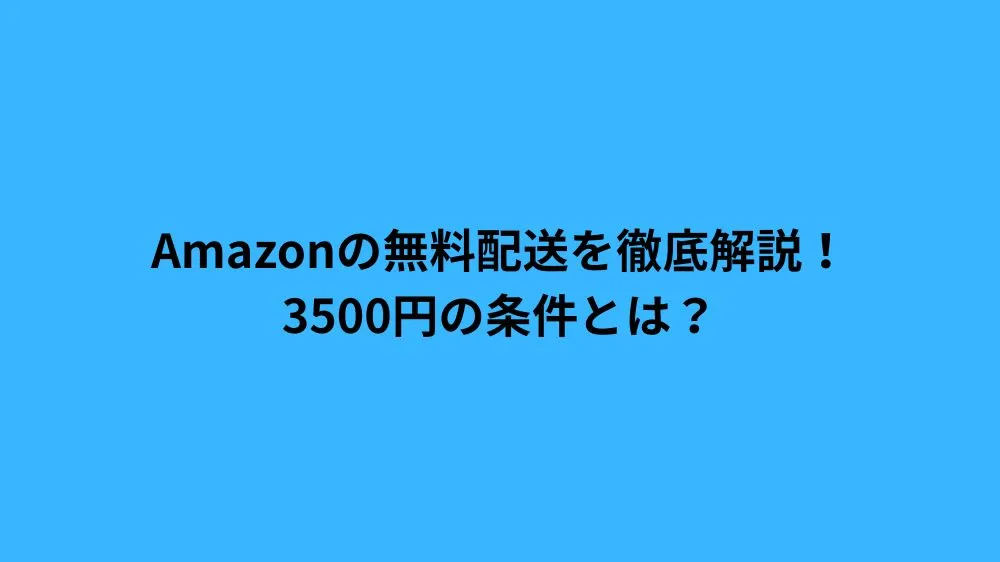Amazonで注文した商品を家族に知られずに受け取りたい、あるいは日中留守がちで宅配便のタイミングが合わない、といった悩みはありませんか。そんな時、「amazonの郵便局留め」が使えたら非常に便利ですよね。
しかし、Amazonの注文で郵便局留めができないケースがあることも事実です。
この記事では、Amazonで家以外で受け取るにはどうすればよいか、郵便局受け取り やり方から、代替案となるコンビニ受け取り やり方まで、具体的な手順を詳細に解説します。
また、マーケットプレイス 郵便局留めの可否、正しい郵便局留め 住所の書き方、さらには局留め ヤマトなど他社の営業所止めについても深く掘り下げていきます。
Amazon 受け取りスポット どうやる?そもそも郵便局留めは禁止されていますか?といった細かな疑問にもお答えし、誰もが安心して利用するためのポイントを網羅します。
※クリックするとAmazonプライム公式サイトに飛びます
※期間内に解約すると料金はかかりません。
本記事の内容
- Amazon発送と出品者発送での郵便局留めの可否の違い
- 郵便局留めができない場合のコンビニ受け取り設定方法
- 出品者に郵便局留めを依頼する際の具体的な手順と注意点
- 正しい郵便局留めの住所の書き方と受け取りに必要なもの
本ページの情報は2025年9月時点の情報です。最新の配信情報は配信サイトにてご確認ください。
amazonの郵便局留めは可能?発送パターンで解説

※画像はイメージです:kamiani作成
ポイント
- Amazonで家以外で受け取るには?
- Amazon発送で郵便局留め できないケース
- 代替案のコンビニ受け取り やり方
- Amazon 受け取りスポット どうやる?
- そもそも郵便局留めは禁止されていますか?
Amazonで家以外で受け取るには?
Amazonで注文した商品を自宅以外の場所で受け取りたい、というニーズは様々なシーンで発生します。
例えば、一人暮らしで日中は不在がちな方、寮やシェアハウスにお住まいの方、あるいは家族へのサプライズプレゼントを秘密にしておきたい場合など、理由は多岐にわたります。
このような場合に役立つのが、自宅外での受け取りサービスです。Amazonでは主に以下の方法が考えられます。
- 郵便局留め: 指定した郵便局の窓口で荷物を受け取る方法。
- コンビニ受け取り: ローソンやファミリーマートなどで荷物を受け取る方法。
- 宅配便営業所止め: ヤマト運輸などの営業所で荷物を受け取る方法。
- 宅配ロッカー(PUDOなど): 駅や商業施設に設置されたロッカーで受け取る方法。
ただし、これらの便利なサービスが常に利用できるわけではありません。利用の可否は、Amazonでの商品の「販売元」と「発送元」の組み合わせによって決まります。
Amazonの売買パターンは大きく分けて以下の3つがあり、この違いを理解することが、希望の受け取り方法を選択する上での第一歩となります。
Amazonの3つの販売・発送パターン
- Amazonが販売し、Amazonが発送する商品
- マーケットプレイス出品者が販売し、Amazonが発送する商品(FBA)
- マーケットプレイス出品者が販売し、出品者が自ら発送する商品
この記事では、これらのパターン別に、どの受け取り方法が利用できるのかを詳しく解説していきます。
Amazon発送で郵便局留め できないケース
結論から明確にお伝えすると、前述の販売パターンのうち、「1. Amazonが販売・発送する商品」と「2. 出品者が販売しAmazonが発送する商品(FBA)」の2パターン、つまりAmazonの物流拠点から発送されるすべての商品は、郵便局留めにすることができません。
その最大の理由は、Amazonが採用している独自の配送システムにあります。Amazonは、購入者の住所、荷物のサイズ、配送の混雑状況などを総合的に判断し、提携する多数の配送業者の中から最適な一社を自動的に割り当てています。
これには日本郵便だけでなく、ヤマト運輸、佐川急便、そして「デリバリープロバイダ」と呼ばれる地域限定の配送業者や、個人事業主が配達する「Amazon Flex」などが含まれます。
郵便局留め住所での注文は絶対におやめください
「郵便局留め」は日本郵便限定のサービスです。そのため、ヤマト運輸や佐川急便など、他の業者に配送が割り当てられた場合、荷物を郵便局に届けることが物理的に不可能です。もし、お届け先住所を無理やり郵便局の所在地にして「〇〇郵便局留め」と記載して注文した場合、荷物は「宛先人不明」として扱われ、最終的にAmazonの倉庫へ返送されます。この際、注文は自動的にキャンセル処理されますが、返金の際に往復の配送料を差し引かれる可能性があるため、絶対に行わないようにしてください。
Amazonから発送される商品で自宅以外での受け取りを希望する場合は、Amazonが公式に提供している「受取スポット」のサービスを利用する必要があります。
代替案のコンビニ受け取り やり方
Amazon発送の商品で郵便局留めが利用できない場合の、最も便利で確実な代替案が「コンビニ受け取り」です。全国に多数存在する主要なコンビニエンスストアで、24時間365日、ご自身の都合の良いタイミングで荷物を受け取れるため、多くの方にとって郵便局留め以上に利便性の高い選択肢と言えるでしょう。
コンビニ受け取りの設定方法は、Amazonの注文プロセス内で非常に簡単に行えます。
設定手順の詳細
- 通常通り、購入したい商品をショッピングカートに入れ、レジに進みます。
- 「お届け先住所の選択」画面が表示されます。登録済みの自宅住所などの下に表示される「新しい受取スポットを検索する」のリンクをクリックします。
- 地図と検索ウィンドウが表示されます。現在地周辺のほか、住所、駅名、ランドマーク(例:「東京駅」)などで受け取りたい場所を検索します。
- 検索結果の中から、利用したいコンビニ(ローソン、ファミリーマートなど)やヤマト運輸の営業所を選択し、「ここで受け取る」ボタンをクリックします。
- 選択した店舗が「お届け先」として設定されていることを最終確認画面で確かめ、注文を完了させます。
商品が指定の店舗に到着すると、Amazonのアカウントに登録されているメールアドレス宛に、件名「Amazon.co.jp ご指定のコンビニでのお受け取りの準備ができました」といった通知が届きます。
メールには、受け取りに必要な「認証キー(お問い合わせ番号と認証番号)」または「バーコード受け取り用のURL」が記載されています。その情報を持って店舗に行き、Loppi(ロッピー)やFamiポートといったマルチメディア端末を操作するか、直接レジでスマホのバーコードを提示することで、スムーズに荷物を受け取ることができます。
Amazon 受け取りスポット どうやる?
前述の「コンビニ受け取り」は、Amazonが公式に提供している「受取スポット」という便利なサービスの包括的な名称の一部です。受取スポットは、コンビニだけでなく、利用者の多様なライフスタイルに対応するため、様々な場所が用意されています。
Amazonが発送する商品であれば、以下の場所を受け取り先に指定可能です。(参照:Amazon.co.jp ヘルプ&カスタマーサービス)
Amazon受取スポットの主な種類と特徴
| 受取スポットの種類 | 主な設置場所 | 特徴・メリット |
| コンビニエンスストア |
| 店舗数が多く24時間受け取り可能。最も利便性が高い。 |
| ヤマト運輸 営業所 | 全国のヤマト運輸直営店 | 対面での受け取りで安心感がある。比較的大きな荷物にも対応。 |
| PUDOステーション |
| 非対面で受け取れる宅配便ロッカー。早朝や深夜でも利用可能。 |
| Amazon Hub | Amazon Hub ロッカー/カウンター | Amazon独自のロッカーや提携店舗のカウンター。都市部を中心に増加中。 |
これらの受取スポットの利用方法は、すべてコンビニ受け取りの手順と同様です。注文時のお届け先選択画面で、希望するスポットを検索して指定するだけで手続きは完了します。
例えば、「仕事帰りに最寄り駅のPUDOロッカーで受け取る」「買い物のついでにスーパーマーケット内のAmazon Hubカウンターで受け取る」といった、ご自身の生活動線に合わせて受け取り場所を自由に設計できるのが最大の魅力です。
Amazon発送の商品を購入する際は、これらの便利なサービスを積極的に活用してみてください。
そもそも郵便局留めは禁止されていますか?
「Amazonのルールとして、郵便局留めは明確に禁止行為なのか?」という疑問についてですが、結論から言うと、Amazonの規約上で「郵便局留めを禁止する」と明記された項目はありません。しかし、これにはパターンに応じた注意深い解釈が必要です。
1. Amazonが発送する商品の場合
前述の通り、これは規約違反という以前の問題で、Amazonの多様な配送業者を利用するシステム上、そして運用上の理由から「対応不可能」というのが実情です。「禁止」という言葉よりも「利用できない仕様」と理解するのが最も正確です。
2. マーケットプレイス出品者が自ら発送する場合
こちらは「出品者との個別の合意があれば可能」な、いわゆるグレーゾーンと言えます。Amazonが出品者に課している基本ポリシーは「注文管理画面に表示された住所にのみ商品を発送すること」です。購入者からの事前の依頼に基づきお届け先を変更すること自体を固く禁じているわけではありません。
非推奨とされる理由とリスク
Amazonがマーケットプレイスでの郵便局留めを推奨しない背景には、トラブル時の責任問題があります。万が一、荷物の不着や受け取り拒否といった問題が発生した際に、「Amazonマーケットプレイス保証」を申請しても、「本来の登録住所外への配送」と判断され、保証の対象外となるリスクがゼロではありません。
そのため、出品者側も購入者側も、ある程度のリスクを自己責任で負うという前提での利用となります。

最終的に、Amazon全体で一律に禁止されているわけではないものの、利用できるのは「出品者が自ら発送し、かつ購入者からの事前の依頼に合意してくれる」という限定的な条件下のみ、と理解しておくことが重要です。
amazonで郵便局留めを利用する具体的な方法

※画像はイメージです:kamiani作成
ポイント
- マーケットプレイスでの郵便局留め依頼
- 正しい郵便局受け取り やり方と手順
- 郵便局留めで指定する住所の書き方
- 局留め ヤマトなど他社の営業所止め
- 郵便局以外の営業所止めも可能か
- 総括:amazon 郵便 局留め活用のポイント
マーケットプレイスでの郵便局留め依頼
Amazon発送の商品では利用できない郵便局留めですが、Amazonマーケットプレイスに出店している販売業者が、自社の拠点から商品を発送する場合(商品ページに「出荷元:〇〇(出品者名)」と表示されている商品)に限り、利用できる可能性が残されています。
ただし、これはあくまで「可能性」であり、いくつかの条件をクリアする必要があります。最大の条件は、その出品者が配送方法として日本郵便を利用しており、かつ購入者からの個別リクエストに柔軟に対応してくれることです。
そのため、自分の判断でいきなり郵便局留めの住所を入力して注文するのは、深刻なトラブルの原因となるため絶対に避けてください。必ず以下の手順を踏み、購入前に出品者からの承諾を得る必要があります。
出品者への事前確認手順
- 購入したい商品の詳細ページを開き、販売価格の下やカートボタンの近くにある出品者名(「販売元:〇〇」)をクリックします。
- 出品者の情報ページに移動したら、「質問する」ボタンを探してクリックします。
- カスタマーサービスのチャットまたはメッセージフォームが開きますので、そこで購入を検討している旨と、郵便局留めでの発送に対応してもらえるかを丁寧に問い合わせます。
問い合わせメッセージの例文
「出品者様
はじめまして。〇〇(あなたのお名前)と申します。
貴社で販売されております「△△(商品名)」の購入を検討しております。
つきましては、大変恐縮なのですが、商品の受け取りを郵便局留めでお願いすることは可能でしょうか。
もし可能でしたら、購入させていただきたく存じます。
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご返信いただけますと幸いです。」
この問い合わせに対し、出品者から「対応可能です」との明確な返事があった場合に限り、注文手続きに進みましょう。出品者が郵便局留めを断るケースも少なくありません。
その理由としては、「ヤマト運輸など特定の配送業者と大口契約を結んでおり、個別対応が難しい」「通常と異なる発送方法はミスやトラブルの原因になる」「過去に受け取り拒否などのトラブルがあったため、局留めは一律で断っている」などが挙げられます。
丁重に断られた場合は、その出品者からの購入での郵便局留めは潔く諦め、別の出品者を探すか、自宅で受け取るようにしましょう。
正しい郵便局受け取り やり方と手順
出品者からの快い承諾を得て、無事に郵便局留めで商品が発送された後、今度は購入者側が正しく荷物を受け取る必要があります。受け取り方の手順と注意点をしっかり確認しておきましょう。
1. 荷物の配送状況を追跡する
最も重要な注意点として、郵便局留めの場合、荷物が指定の郵便局に到着しても、郵便局から電話やハガキでの「到着のお知らせ」は一切ありません。荷物の状況は、すべて自分で能動的に確認する必要があります。
出品者から発送通知とともに伝えられる「追跡番号(お問い合わせ番号)」を使い、日本郵便の追跡サービスサイトでこまめに状況を確認しましょう。「お届け先にお届け済み」や「窓口でお渡し」といったステータスに更新されたら、受け取りが可能な合図です。
2. 指定した郵便局の窓口へ行く
荷物を受け取るためには、指定した郵便局の郵便窓口、または時間外対応をしている「ゆうゆう窓口」へ行きます。
特にゆうゆう窓口は、通常の郵便窓口が閉まっている平日の夜間や土日祝日も営業している場合が多く便利ですが、営業時間は郵便局によって大きく異なります。訪問前に日本郵便の公式サイトなどで必ず営業時間を確認しておきましょう。
3. 受け取りに必要なものを準備する
窓口での受け取りの際には、以下の3点が必須となります。一つでも忘れると受け取れない可能性があるため、家を出る前に必ず確認してください。
郵便局留め受け取りの三種の神器
- 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど、氏名と現住所が確認できる公的な身分証明書。(学生証や社員証は不可の場合があります)
- 荷物の追跡番号(お問い合わせ番号):11桁または13桁の番号です。荷物を特定し、スムーズに探し出してもらうために必要です。スマホのスクリーンショットやメモで提示できるようにしておきましょう。
- 印鑑(またはサイン):荷物を受け取った証として、受領書に押印または署名をします。シャチハタでも問題ありません。
また、荷物の保管期間は、日本郵便の規定により、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間と定められています。この期間(土日祝日も含む)を過ぎると、荷物は差出人である出品者の元へ返送されてしまいますので、計画的に受け取りに行くようにしましょう。
郵便局留めで指定する住所の書き方
出品者から郵便局留めの許可を得た後、注文手続きの際に最も重要になるのが「お届け先住所」の入力です。ここで書き方を間違えてしまうと、荷物が正しく届かない、あるいは返送されてしまうといったトラブルに繋がります。以下の公式な形式に沿って、正確に入力してください。
以下の項目を、Amazonのお届け先入力フォームの各欄に正確に割り振って入力するのが最も確実です。
Amazon注文時における郵便局留めの正しい住所フォーマット
- 郵便番号: 〒〇〇〇-〇〇〇〇(【重要】受け取りたい郵便局の郵便番号)
- 都道府県・市区町村: 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇(【重要】受け取りたい郵便局の所在地)
- それ以降の住所: 〇〇 X-Y-Z(郵便局の番地など)
- アパート名・マンション名など: 〇〇郵便局留め (この記載が必須です)
- 氏名: あなたの氏名(フルネーム)
- 電話番号: あなたの連絡先電話番号
最大のポイントは、ご自身の自宅の郵便番号や住所ではなく、受け取りを希望する郵便局の情報を正確に入力することです。そして、「アパート名」などを入力する欄に「〇〇郵便局留め」という一文を明確に加えることで、配達員がこれは局留めの荷物であると確実に認識できます。

局留め ヤマトなど他社の営業所止め
「郵便局留め」は日本郵便が提供する独自のサービスですが、他の主要な宅配便業者にも、同様のコンセプトのサービスが存在します。それが「営業所止め」です。
このサービスは、荷物をご自宅に配達する代わりに、指定した配送業者の営業所(サービスセンターやデポなど)で一時的に保管してもらい、受取人が好きなタイミングで直接取りに行くというものです。仕組みは郵便局留めと全く同じです。
これも、Amazonマーケットプレイスの出品者が自ら商品を発送する場合で、その出品者がメインの配送業者としてヤマト運輸や佐川急便を利用していれば、交渉次第で利用できる可能性があります。
出品者に問い合わせる際は、正しいサービス名で依頼するとコミュニケーションがよりスムーズになります。
主要な宅配便業者のサービス正式名称
- 日本郵便: 郵便局留め
- ヤマト運輸: 営業所止置きサービス
- 佐川急便: 営業所受取サービス
出品者によっては、「郵便局は使わないけど、いつも使っているヤマトの営業所止めなら対応できますよ」といったケースも考えられます。郵便局留めに固執せず、代替案として営業所止めが可能か尋ねてみるのも有効な手段です。
郵便局以外の営業所止めも可能か
前項の通り、マーケットプレイスの出品者が個別に対応してくれるのであれば、郵便局以外のヤマト運輸や佐川急便の営業所で荷物を受け取ることも十分に可能です。
依頼から受け取りまでの基本的な流れは、郵便局留めの場合と全く同じです。まずは購入前に出品者へ「ヤマト運輸の営業所止めでの発送は可能でしょうか?」といった形で問い合わせを行い、明確な許可を得てから注文手続きに進みます。
お届け先住所の入力方法も、郵便局留めの考え方を応用します。つまり、ご自身の住所ではなく、受け取りたい営業所の情報を入力します。
ヤマト運輸の営業所止めを依頼する場合の住所入力例
| 項目 | 入力内容の具体例 | 注意点 |
| 郵便番号 | 受け取りたい営業所の郵便番号 | ヤマト運輸の公式サイトで正確な番号を確認 |
| 住所 | 受け取りたい営業所の住所 + 「〇〇センター止め」 | 営業所の正式名称(例:宅急便センター)と「止め」を明記 |
| 氏名 | あなたの氏名(フルネーム) | 本人確認書類と一致していること |
| 電話番号 | あなたの連絡先電話番号 | 不備があった際の連絡に使われる可能性あり |
なお、Amazonが発送する商品の場合は、前述の「受取スポット」の選択肢としてヤマト運輸の営業所が含まれているため、そちらを利用するのが公式で最も簡単な方法となります。出品者への交渉が必要なのは、あくまで出品者が自ら発送する場合に限られます。
総括:amazon 郵便 局留め活用のポイント

※画像はイメージです:kamiani作成
この記事で解説してきた、Amazonでの郵便局留め、および自宅外受け取りに関する重要なポイントを以下に総まとめします。ご自身の状況に応じて最適な受け取り方法を判断し、トラブルなく安全に利用するためのチェックリストとしてご活用ください。
ポイント
- Amazonが発送する商品はシステム上、郵便局留めは利用できない
- Amazon発送商品の自宅外受け取りは公式の「受取スポット」を利用する
- 受取スポットにはコンビニ、ヤマト営業所、宅配ロッカーなどがある
- 受取スポットの指定は注文時のお届け先選択画面から簡単に行える
- マーケットプレイス出品者が自ら発送する商品は郵便局留めが可能な場合がある
- 出品者に郵便局留めを依頼する際は必ず購入前にメッセージで許可を得る
- 出品者から明確な承諾を得た場合に限り、郵便局留めの住所で注文する
- 郵便局留めの住所は受け取りたい郵便局の郵便番号と所在地を正確に入力する
- 住所欄に「〇〇郵便局留め」と明確に記載することが最も重要
- 郵便局に荷物が到着しても郵便局からの連絡は一切来ない
- 荷物の状況は必ず自分で追跡番号を使って確認する必要がある
- 郵便局での保管期間は到着日の翌日から10日間と定められている
- 受け取りには「本人確認書類」「追跡番号」「印鑑」の3点が必須
- ヤマト運輸や佐川急便にも同様の「営業所止め」サービスが存在する
- 営業所止めも郵便局留めと同様に、出品者への事前確認が不可欠
- トラブルを避けるためにも、出品者の許可なく特殊な住所を指定して注文するのは絶対に行わない
- どの受け取り方法が使えるかは、まず商品ページの「販売元」と「出荷元」を確認することから始まる
※クリックするとAmazonプライム公式サイトに飛びます
※期間内に解約すると料金はかかりません。