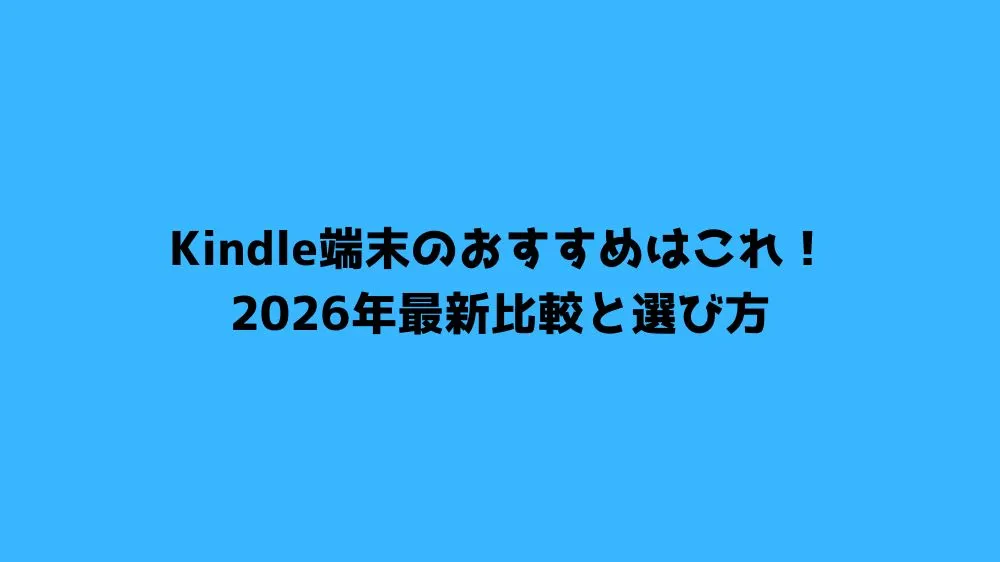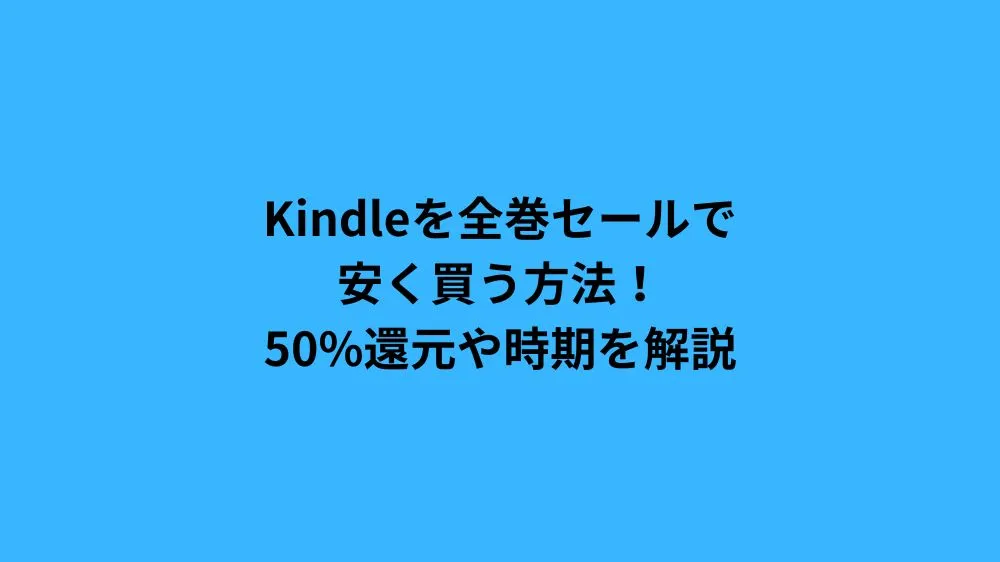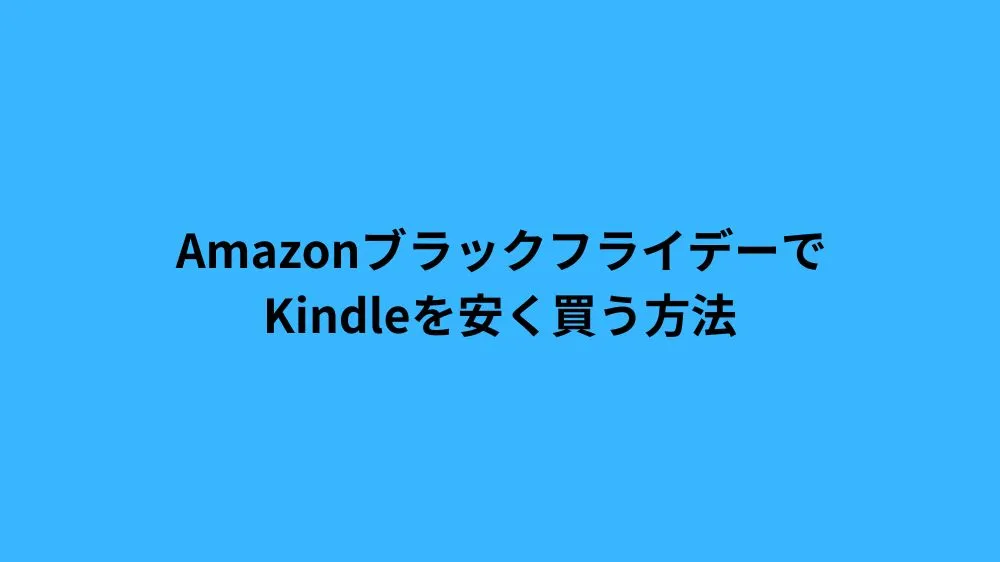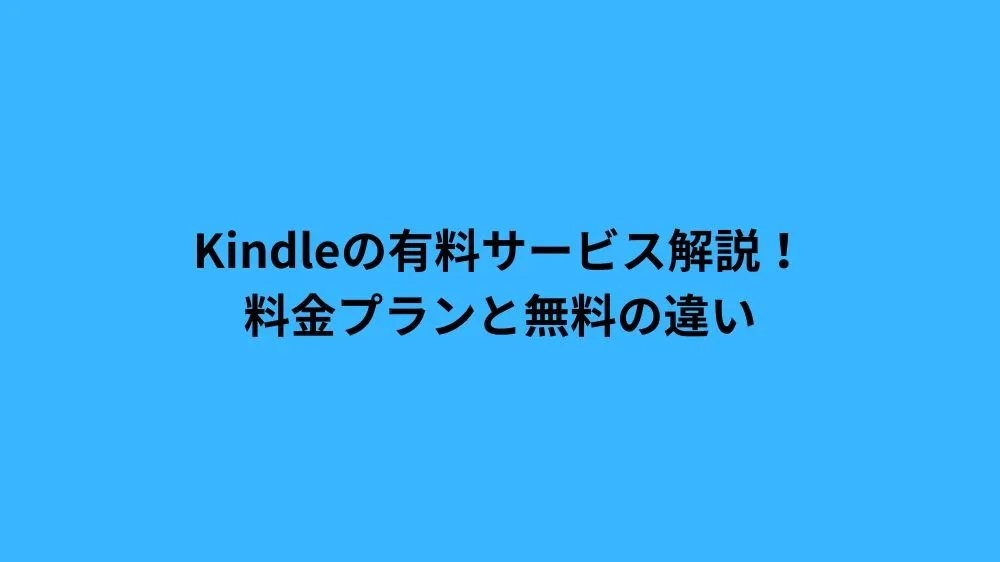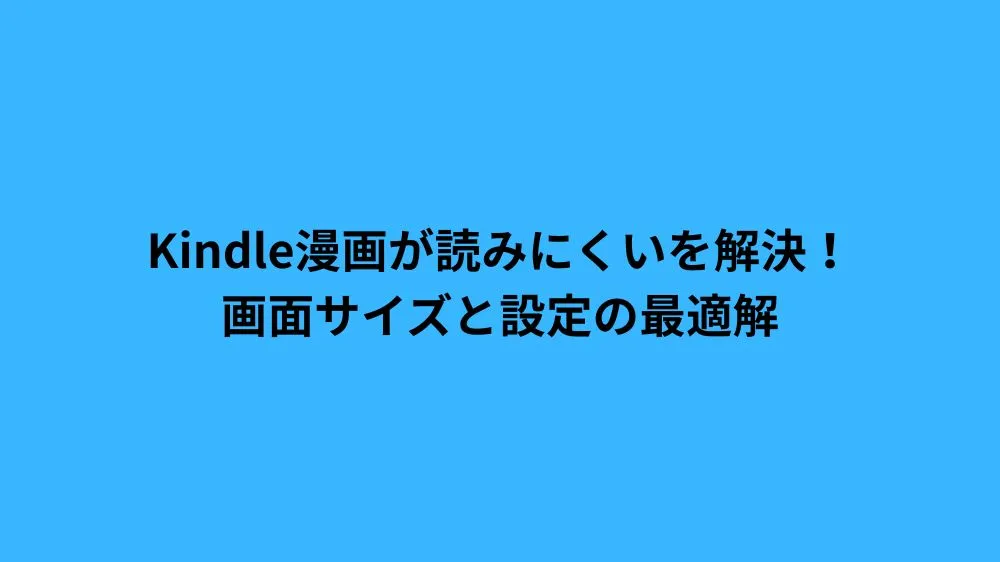Kindleで読書を始めたいけど、「kindleの有料サービスって結局何があるの?」「Unlimitedの月額料金はいくらなんだろう…」「Amazonプライム会員なら割引があるの?」といった疑問や、「Prime Readingとの違いがよくわからない」と感じている方、結構多いんじゃないかなと思います。
Kindleの料金体系って、読み放題プランや端末代、個別の書籍購入が組み合わさっていて、パッと見ただけでは少し複雑に見えますよね。どの部分が「有料」で、どこまでが「無料」なのか、ハッキリさせたいと思うのは当然のことかなと思います。
この記事では、Kindleの有料プランである「Kindle Unlimited」の料金体系や、お得なキャンペーン、気になる年間プランの有無、そして読み放題の10冊制限について、私の知っている範囲で詳しく解説していきます。
さらに、プラン料金以外に費用がかかるのか、例えばkindle端末は買う必要があるのか、無料アプリや青空文庫など、無料で楽しめる範囲はどこまでなのかも掘り下げます。
あわせて、クレジットカードなしでも使える携帯決済(キャリア決済)などの支払い方法についてもしっかりまとめていきますね。
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません
本記事の内容
- Kindle有料プラン(Unlimited)の料金と仕組み
- Prime Readingとの明確な違い
- 有料プラン以外にかかる費用(端末代など)
- クレカなしでもOKな支払い方法の種類
本ページの情報は2025年11月時点の情報です。最新の配信情報は配信サイトにてご確認ください。
kindle有料プランの料金体系
まず、多くの人が「Kindleの有料サービス」としてイメージするのが、月額制の読み放題プラン「Kindle Unlimited」だと思います。これはKindleエコシステムにおける中核的なサブスクリプションサービスですね。
ここでは、このプランの料金や仕組みについて、メリットや注意点を含めて詳しく見ていきましょう。
Unlimitedの月額料金はいくら?
Kindle Unlimitedの基本的な料金プランは、月額980円(税込)です 。この料金で、小説、漫画、雑誌、ビジネス書、実用書、ラノベなど、非常に幅広いジャンルの対象タイトル(公称では500万冊以上 )が読み放題になります。
この月額980円という価格設定が、ご自身の読書スタイルに見合うかどうか(=元が取れるか)は、一番気になるところですよね。一般的な書籍の価格から、コストパフォーマンスの分岐点を試算してみました。
月額980円のコスパ目安
- ビジネス書 (1冊1,500円~2,000円程度 ): こうした単価の高い本なら、月に1冊読むだけで、もう元が取れてしまう計算になりますね。
- 小説 (1冊800円~1,500円程度 ): 月に1冊だと少し足りないかもしれませんが、2冊読めば十分お得と言えそうです。
- 漫画 (1巻500円~700円程度 ): 漫画好きの方なら、月に2~3巻読めば元が取れます。シリーズものを一気読みしたい時などに特に強いですね。
- 雑誌 (1冊500円~1,000円程度 ): 普段から雑誌を定期購読している方なら、1~2冊読むだけで月額料金に達します。色々な雑誌をつまみ食いできるのも魅力です。
このように、毎月コンスタントに何かしらの本や雑誌を読む習慣がある方にとっては、かなり魅力的な価格設定かなと思います。逆に、読むのが数ヶ月に1冊程度という方だと、都度購入(後述します)の方が安上がりになるかもしれません。
お得な年間プランは存在する?
他の多くのサブスクリプションサービス(動画配信など)では、月額プランより割安になる「年間プラン」が用意されていることが多いですよね。
Kindle Unlimitedにもそれがあるかというと、残念ながら、誰もが自由に選べる標準的な年間プランは用意されていません 。基本は月額980円のプランのみとなります。
ただし、これで話が終わりじゃないのがAmazonらしいところで、ちょっと特殊なケースが存在します。
一部の既存ユーザーや、特定の条件(詳細は非公開です)を満たした人向けに、Amazonから非公開の特別プランが個別に提示されることがあるようです。
これには、「年額9,800円(月額換算で約817円)」といった、実質的に2ヶ月分お得になるプランが含まれることがあるみたいです。
ただ、これはあくまで「あなたの特別プラン」として表示された人のみが対象の限定オファーです。どういう条件で表示されるのか(例:長期利用者向け、一度解約した人向けの引き止め策など)はハッキリしていないので、基本的には月額プランがメインと考えるのが良さそうです。
プライム会員の割引とキャンペーン
「Amazonプライム会員なら、Kindle Unlimitedも安くなるのでは?」と期待しますよね。私もAmazonのサービスをよく使うので、当然そう思っていました。
ですが、これはよくある誤解の一つで、結論から言うと、プライム会員向けの標準的な月額割引はありません。プライム会員であっても、非会員であっても、Kindle Unlimitedの基本料金は同じ月額980円です。これは独立したサービスとして位置づけられています。
ただし、ガッカリするのはまだ早いです。標準割引はない代わりに、プライム会員「限定」のプロモーション(キャンペーン)が非常に頻繁に実施されています。
よく見かけるキャンペーン例
- 3ヶ月無料(0円): プライムデーやプライム感謝祭といった、Amazonの大型セール時によく見かける、最もお得なキャンペーンです 。プライム会員で未加入なら、このタイミングが最大の狙い目ですね。
- 3ヶ月99円 / 2ヶ月99円: 「ほぼ無料」で長期間試せるキャンペーンです。ブラックフライデーセール や、それ以外の時期でも不定期に開催されている印象です。
- 2ヶ月199円: こちらも非常にお得なパターンのひとつです。
- 初回30日間無料体験: 上記のような大型キャンペーンがない時期でも、初めて利用する人向けに「30日間無料体験」が標準で用意されていることが多いです。
また、FireタブレットやKindleの電子書籍リーダー端末を購入する際に、オプションとして「Kindle Unlimited 3ヶ月無料」がバンドル(付帯)されていることもあります 。
なので、標準割引はなくても、入会のタイミング次第で実質的にお得に始められるチャンスは非常に多いと言えますね。利用を検討しているなら、まずはこうしたキャンペーンが実施されていないかチェックするのが鉄則です。

Prime Readingとの決定的な違い
Kindleの料金体系で一番混乱しやすいポイントが、この「Kindle Unlimited」と「Prime Reading(プライムリーディング)」の違いだと思います。私も最初は「何が違うの?」と戸惑いました。
この2つ、サービス内容(本が読み放題)が似ているようで、実は立ち位置が全く異なります。一番大きな違いは「コスト」と「読める冊数(コンテンツ規模)」です。
| 項目 | Kindle Unlimited | Prime Reading |
| 料金 | 月額980円(税込) | プライム会費に含まれる (追加料金0円) |
| 対象者 | すべてのAmazonユーザー | Amazonプライム会員 限定 |
| 対象冊数 | 500万冊以上 | 数百~数千冊程度(変動あり) |
| 同時利用 | 10冊まで | 10冊まで |
つまり、Prime Readingはプライム会員の「特典(ベネフィット)」のひとつで、プライム会費を払っていれば追加料金なしで使えるサービスです。対してKindle Unlimitedは、たとえプライム会員であっても別途月額980円が必要な「独立した有料サブスクリプション」なんです。
ではなぜ混乱するのかというと、最大の原因は、どちらも「同時に10冊までダウンロード可能」という利用上の仕組み(UI/UX)がほぼ同じだからですね。
プライム会員がPrime Readingで「10冊まで借りて、読み終わったら返して次を借りる」という体験をした後、Unlimitedに登録しても全く同じ操作感なので、「同じサービスなのになぜ片方は有料?」となってしまうわけです。
「借りられる図書館の規模が全然違う」と考えると分かりやすいかもしれません。Prime Readingはプライム会員向けの「小さな図書室(お試し版)」、Unlimitedは月額料金を払って利用する「巨大な国立図書館」といったイメージでしょうか。
読み放題の10冊制限と対象範囲
月額980円の有料サービスであるKindle Unlimitedですが、万能というわけではなく、いくつか注意すべき「制限」もあります。ここを理解しておかないと「思っていたのと違った」となりかねないので、重要です。
1. 同時ダウンロードは10冊まで
これはPrime Readingとも共通する重要なルールですが、一度にダウンロードして「借りている」状態にできるのは、最大10冊までです。
「10冊制限」の正しい理解
この制限は、「月に10冊までしか読めない」という意味ではありません。あくまで「自分のライブラリ(本棚)に同時に置いておけるのが10冊まで」という意味です。
もし11冊目を読みたくなったら、すでにダウンロード済みの10冊のうち、読み終わった本などを手動で「利用終了」(削除または返却)操作をする必要があります 。利用終了して枠を1つ空ければ、すぐに新しい本をダウンロードできます。なので、月に何十冊読んでも問題ありません。
漫画のシリーズなどを一気にダウンロードしようとすると、すぐに10冊の枠が埋まってしまうので、この「入れ替え作業」が少し手間に感じるかもしれない、という点は覚えておくと良いですね。
2. すべての本が対象ではない
「500万冊以上」と聞くと膨大ですが、これはKindleストアで販売されているすべての書籍が対象というわけでは、もちろんありません。あくまで「対象作品」が読み放題になるサービスです。
特に、発売されたばかりの話題の新刊や、人気のベストセラーの多くは読み放題の対象外となっていることが多いです。これは、出版社や著者の収益モデルとして、新刊はまず「都度購入」で販売したいという意向があるためだと考えられます。
「あの最新刊が読みたかったのに、Unlimitedの対象外だった…」ということは日常的に起こります。これらの本を読みたい場合は、Unlimitedの月額料金とは別に、個別にその書籍を購入(第4部で解説する「都度購入」)する必要があります。
kindleの有料はプラン以外にもある?
ここまで月額プラン「Kindle Unlimited」を中心に見てきましたが、Kindleでお金がかかるのは、このサブスクリプションだけではありません。それ以外にも「有料」となる要素がいくつかあります。
ここでは、プラン以外のコストについて、そして逆に「無料」で使える範囲について見ていきましょう。
kindle端末は買う必要がある?
「Kindleって、あの黒い専用端末を買わないと読めないの?」と思っている方もいるかもしれません。特に初めて電子書籍に触れる方は、そう考えがちですよね。
結論から言うと、専用端末の購入は100%オプション(任意)です。必須ではまったくありません。
なぜなら、Amazonはスマートフォン(iPhone/Android)やタブレット(iPad/Fire)、PC(Windows/Mac)向けに、「Kindle無料アプリ」を公式に提供しているからです 。
この無料アプリ をお手持ちのデバイスにインストールして、自分のAmazonアカウントでログインしさえすれば、すぐにKindleの本を購入したり、Unlimitedの本を読んだりすることができます。
こうしたメリットに価値を感じる人が「一回限りの有料オプション」として購入するわけですね。価格はベーシックモデルで約2万円 、防水機能などが付いた人気のPaperwhiteで約2万8千円 くらいが目安です(2025年11月時点)。
ちなみに、昔は「Kindle Oasis WiFi+4G LTE」というモデルに、本体価格に4G回線の通信費が実質含まれている(通信費無料でダウンロードし放題)、ちょっと特殊な有料モデルも存在しました。
アプリや青空文庫など無料の範囲
Kindleには「有料」だけでなく、「無料」で楽しめる範囲もきちんと用意されています。ここを使いこなすだけでも、かなり読書ライフが充実しますよ。
1. Kindle無料アプリ
まず、先ほども触れたとおり、Kindleの読書プラットフォーム(アプリ)自体は完全に無料です 。アプリをダウンロードしたり、利用したりするのにお金は一切かかりません。
2. 「0円」で販売されている書籍
次に、Kindleストアには、UnlimitedやPrime Readingの対象かどうかに関わらず、販売価格が「0円」に設定されている書籍も存在します。
これは、著者や出版社がプロモーション(シリーズの1巻目だけ無料など)のために提供しているケースや、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)で個人著者が戦略的に無料にしているケースなどがあります。
これらは有料プランに加入する必要なく、誰でも「購入(0円で)」して読むことができます 。
3. 青空文庫(パブリックドメイン)
そして、私が特におすすめしたいのが「青空文庫」の活用です。
「青空文庫」は、著作権が消滅した(パブリックドメインの)文学作品などを集めて電子化しているインターネット上の電子図書館です 。Kindleストアは、この青空文庫の膨大なコレクションにしっかり対応しています。
日本では、著作権は原則として著作者の死後70年間保護されます(出典:文化庁「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」)。この期間が経過した夏目漱石、芥川龍之介、太宰治といった文豪たちの名作が、すべて無料で読めてしまうわけです。
Kindleアプリ内の検索窓で「青空文庫」と入力し、読みたい作品を選んでダウンロードするだけです 。これだけでも、Kindleアプリをインストールする価値は十分あると思いますね。
都度購入と「試し読み」機能
Kindleの最も基本的で、古くからある利用方法は、サブスクリプションではなく「都度購入(都度課金)」です。つまり、読みたい本を1冊ずつ購入する、街の本屋さんと同じ仕組みですね。
Kindle Unlimitedの対象外である新刊やベストセラーの多くは、この方法で購入することになります。Unlimitedはあくまで「利用権(借りている状態)」ですが、都度購入した本は自分のものとして(Amazonのアカウントに紐づく形で)所有できます。
「でも、電子書籍って中身が見れないと不安…」と思いますよね。紙の本ならパラパラとめくって確認できますが、電子書籍ではそれができません。そのための機能が「無料サンプル(試し読み)」です。
書籍の詳細ページにある「今すぐ無料サンプルを送信」というボタンを押す(タップする)だけで、その本の冒頭部分が自分のKindleアプリや端末に自動で送信されます。
ちなみに、この無料サンプルで「どこまで読めるか(何ページ読めるか)」は、出版社や著者側が自動的に設定する仕組みになっていて、ユーザー側で選ぶことはできません。
また、Kindleストアでは「ブラックフライデーセール」 や「双葉社コミックSALE」 、「堂場瞬一大量割引フェア」 といった割引キャンペーンが年間を通じて頻繁に行われています。
月額980円のUnlimitedには入らず、読みたい本をウィッシュリストに入れておき、こうした定期的なセールを狙って安価に「都度購入」する、というのも非常に賢い使い方の一つかなと思います。
余談ですが、KDP(個人出版)の価格設定には、ロイヤリティ(印税)が70%になる価格帯(250円~1,250円)というものが存在し 、多くのインディーズ書籍がこの範囲で価格を決めがちな、という裏事情もあったりします。
支払い方法の種類(クレカなし)
Kindleの各種有料サービス(Unlimited、端末、都度購入)の支払いですが、クレジットカードを持っていない方でも利用できる方法がしっかり用意されています。学生さんや、カード利用に抵抗がある方でも安心ですね。
Amazon(Kindle)で利用できる支払い方法を一覧にしてみました。
| 支払いカテゴリ | 具体的な方法 |
| カード決済 | クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード |
| 携帯決済 (キャリア決済) | d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い など |
| あと払い (BNPL) | あと払い (Paidy) |
| Amazonエコシステム | Amazonギフトカード(残高) 、Amazonポイント |
| その他 | PayPay |
このように、Amazonギフトカード(コンビニなどで購入可能)や携帯決済、PayPayなど、かなり柔軟に対応しているのがわかりますね。
携帯決済(キャリア決済)の詳細
クレジットカードを使いたくない方にとって、特に便利なのが「携帯決済(キャリア決済)」かなと思います。これは、Kindle本の購入代金などを、月々の携帯電話料金とまとめて支払う方法です。事前にチャージする手間もありません。
以下の主要キャリア(および関連サービス)に対応しています。
- NTTドコモ(d払い)
- au(auかんたん決済)
- ソフトバンク(ソフトバンクまとめて支払い)
- ワイモバイル(ワイモバイルまとめて支払い)
- UQ mobile(auかんたん決済)
ご自身が契約しているキャリアがあれば、支払い方法として設定しておくとスムーズです。
携帯決済とPaidyの注意点
ただし、携帯決済にはキャリアや契約者の年齢によって、月々の利用限度額が設定されている場合があるので、その点は事前にご自身のキャリア設定を確認しておくと安心です。
また、もう一つのクレカなし決済「あと払い(ペイディ)」を選んだ場合、清算方法を「コンビニ払い」にすると、手数料(税込356円など)が発生することがあるので、この点も注意が必要ですね。
支払い方法の優先順位と注意点
Kindleの支払いには、知っておかないと「あれ?」となる、ちょっとした「落とし穴」とも言える仕様があります。それは、支払い方法の優先順位が固定されていることです。
Kindle本の購入時には、以下の順番で自動的に支払い方法が選択されます。ユーザーがこの順番を自由に変更することはできません。
Kindle支払い 優先順位
- Amazonクーポン
- Amazonポイント
- Amazonギフト券(ギフトカード残高)
- クレジットカード、携帯決済など(設定された1-Click支払い方法)
※この優先順位はユーザー側で変更できません。
これがなぜ問題かというと、例えば「Amazonポイントを5,000ポイント貯めて、次の大きな買い物のためにとっておこう!」と思っていたのに、500円のKindle本を買った瞬間に意図せずポイントが500ポイント自動で消費されてしまう、ということが起こるからです。
ギフトカード残高も同様です。でも、これはちゃんと回避策も用意されています。知っていれば防げます。
Amazonギフトカードを温存する方法
ギフトカード残高をKindle購入に自動で使われたくない場合は、設定で変更できます。アカウントサービスの「コンテンツと端末の管理」から「設定」に進み、「Kindleの支払い設定」を開きます。「お支払い方法の編集」を選択し、「ギフト券」のチェックを外しておけばOKです 。
Amazonポイントを温存する方法
こちらは設定では変更できません。Kindle本の購入確定画面(最後の「購入」ボタンを押す画面)で、「[ポイントを利用する]」というチェックボックスが表示されます。
ポイントを使いたくない場合は、購入のたびに手動でそこのチェックを外す必要があります。うっかり忘れないように注意したいですね。
あなたに合うkindle 有料の選び方
ここまで、Kindleの有料サービスについて、プラン料金から端末、支払い方法まで色々見てきました。
結局、どの「kindleの有料」サービスを選ぶかは、ご自身の読書スタイルによって決めるのが一番かなと思います。最後に、パターン別におすすめの選び方をまとめてみますね。
読書スタイル別:おすすめの選択肢
- 【パターンA】月に何冊もコンスタントに読む人
雑誌や漫画、ビジネス書など、ジャンルを問わず毎月コンスタントに読む方。このタイプなら、月額980円の「Kindle Unlimited」が断然おすすめです。月に2~3冊読めば元が取れる可能性が高いです。まずはキャンペーンを利用してお得に試してみて、自分の読みたい本がラインナップにどれくらいあるか確認するのが良いと思います。 - 【パターンB】読みたい本がハッキリ決まっている人(新刊・ベストセラー中心)
読むのは話題の新刊や、好きな作家のベストセラーが中心という方。これらの本はUnlimitedの対象外が多いため、Unlimitedには入らず、「都度購入」がメインになりますね。Kindleストアの割引セール のタイミングを狙ったり、試し読み を活用したりするのが賢い方法です。 - 【パターンC】Amazonプライム会員で、たまに読書する程度の人
プライム会員だけど、本はそこまで頻繁には読まないという方。このタイプは、まずは追加料金0円の「Prime Reading」 の範囲内で楽しむのがおすすめです。対象は数百~数千冊と少なめですが、無料で使える特典としては十分です。それで物足りなくなったら、その時に初めてUnlimitedを検討するのが良いでしょう。
もちろん、これらに加えて「Kindle無料アプリ」と「青空文庫」 の活用は、全パターン共通で非常におすすめです。
Kindleは、完全無料で楽しむ方法から、自分の読書量に合わせて最適な有料プランを選べる、非常に柔軟なプラットフォームですね。
この記事で紹介した情報は、執筆時点(2025年11月現在)のものです。料金体系やキャンペーンの詳細、対象となる冊数などは変更される可能性があるため、最新の正確な情報は必ずAmazonの公式サイトでご確認いただくようお願いします。
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません