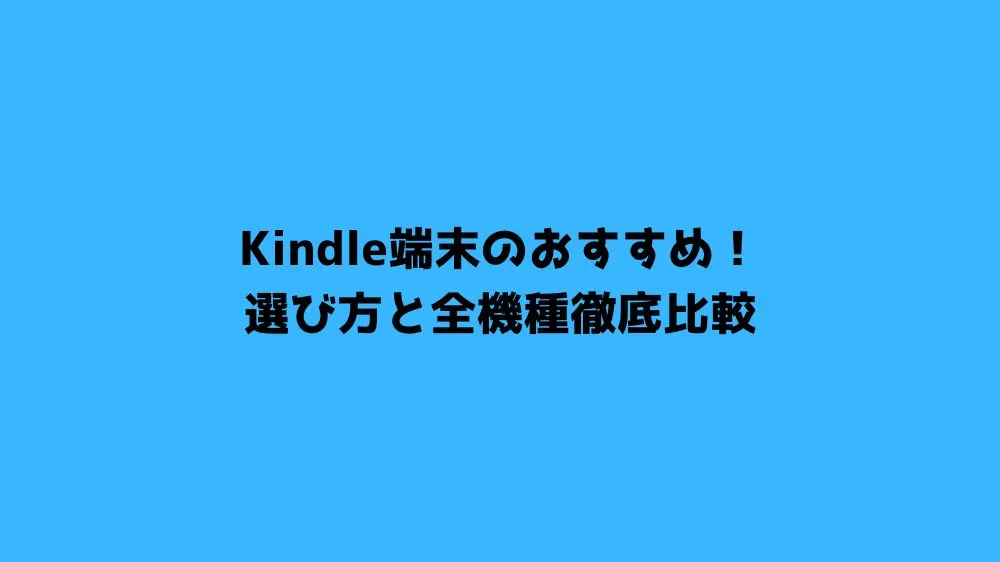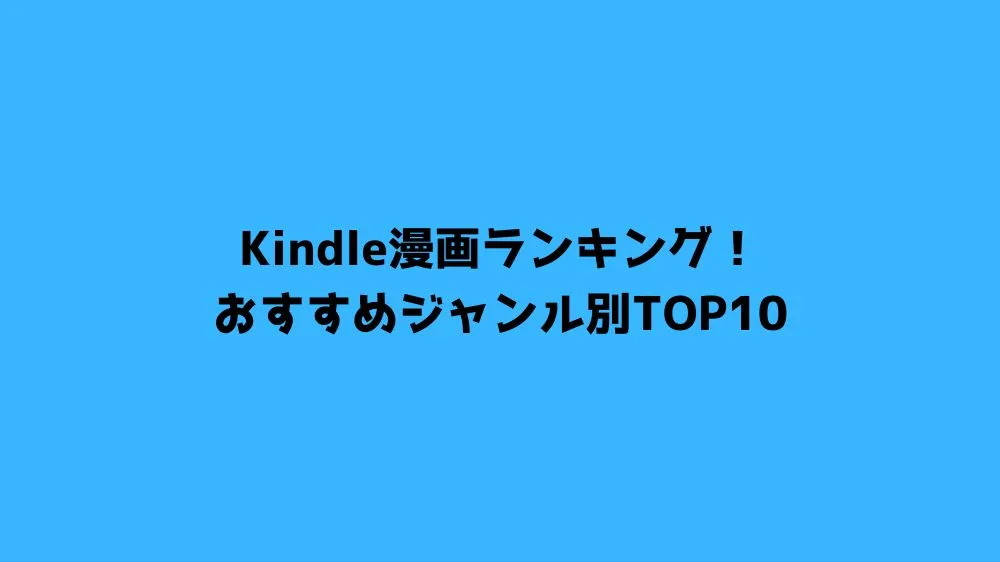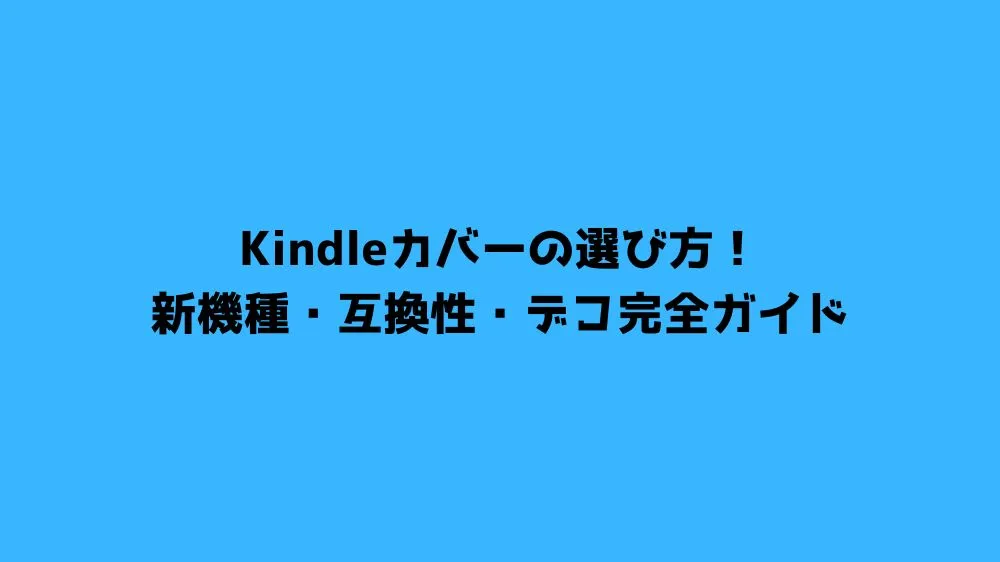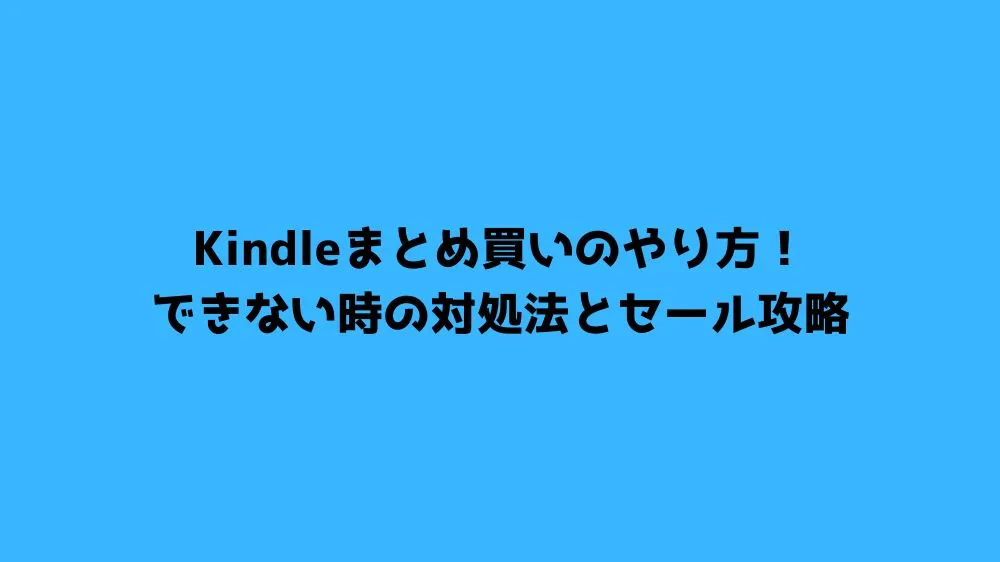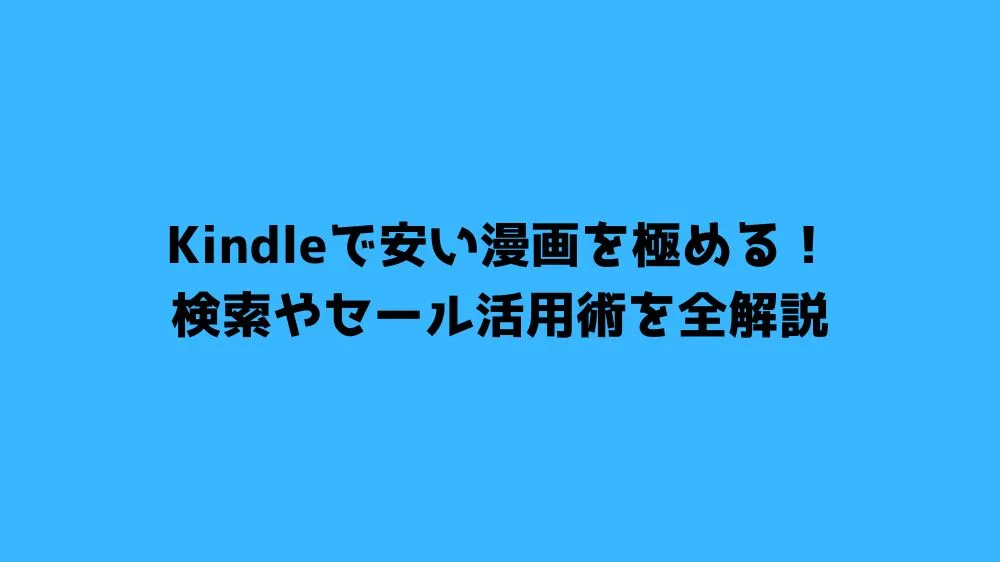部屋がだんだん紙の本で埋まってきて、「この蔵書、ぜんぶKindleに入ったら最高なのに…」なんて思ったこと、ありませんか?
私自身、まさにそれで「kindleの自炊」について色々調べ始めたんですよね。でも、いざ調べてみると、kindle 自炊のやり方はもちろん、スキャナをどうするか、そもそも著作権って大丈夫なの?とか、自炊 代行サービスは違法じゃないの?といった疑問が次々に出てきて。
PDF化すればいいのか、いや待てよ、裁断しない方法もあるらしいぞ?と、情報が溢れていてちょっと混乱しました。スキャンした後のファイル形式は何がベストなのか、どうやってKindle本体に入れるのか、技術的なハードルも高そうに見えますよね。
この記事では、そんな「kindle 自炊」に興味を持ち始めた人が、まず知っておくべき法的な注意点や、実際のファイル形式、転送の方法といった基本情報を、私なりに整理してみました。自炊に踏出す前の「?」を解消するお手伝いができれば嬉しいです。
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません
本記事の内容
- Kindle自炊に関する法的な注意点(著作権)
- 本を裁断する方法と、裁断しない方法の違い
- 自炊に適したファイル形式(PDF, EPUB, ZIPなど)
- 自炊データをKindleに転送する具体的な手順
本ページの情報は2025年11月時点の情報です。最新の配信情報は配信サイトにてご確認ください。
kindle自炊の法的リスクと準備
Kindle自炊を始めよう!と思った時、まず最初にクリアにしておかないといけないのが「それって法律的にOKなの?」という点ですよね。機材を揃える前に、この「著作権」に関する基本と、自炊の方法(裁断する?しない?)について見ていきましょう。
ここを曖昧にしたまま進めると、後でトラブルになる可能性もあるので、しっかり押さえておきたいところです。
KindleでPDF化したら著作権違反になる?
いきなり核心的な話ですが、「自分が所有している本を、自分自身でスキャン(PDF化)して、自分だけで読む」という行為は、日本の著作権法で認められている「私的複製」の範囲内とされています。
これは著作権法の第30条第1項というところで、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とするなら、使う本人が複製してOK、とされているんですね。
なので、自分で買った本を自分でスキャンして、自分のKindleに入れて読む。これはOK、ということになります。
ちなみに、判例の補足として「秘書など、補助者ないし手足といえる者に頼むのは大丈夫」とも言及されている ので、例えば家族がスキャン作業を手伝う程度なら、この範囲内と解釈できるかもしれません。ただし、ここでめちゃくちゃ大事なルールがあります。
自炊データの取り扱いには厳重注意!
私的複製の範囲で作成したデータ(PDFなど)であっても、それを友人にあげたり、ネットで共有・販売したり、ファイル交換ソフトで公開したりする行為は「私的複製」の範囲を完全に超えており、著作権侵害(違法)となります 。
「自分だけ」というルールは、絶対に守らないといけないポイントですね。
PDF化バレることはあるのか?
前の項目と関連しますが、「PDF化 バレる」という心配をしている方もいるかもしれません。これはおそらく、「私的複製」の範囲を超えた使い方(共有やアップロードなど)を想定しているのかなと思います。
「バレるか、バレないか」という議論自体が、すでに危険な領域に足を踏み入れている証拠かも…。
先ほども書いた通り、作成したデータを自分以外の誰かが見られる状態にすることは、著作権法に触れる可能性が非常に高いです。例えば、ファイル交換ソフトなどで公開すれば、技術的に追跡されて法的な責任を問われるリスクは当然あります。
でも、問題の本質はそこじゃないかなと私は思います。技術的にバレる・バレないの問題ではなく、「作ったデータは、絶対に自分だけで使う」という大原則を守るという、本や著者へのリスペクトの問題だと考えています。
このルールさえ守っていれば、「バレるかも」と心配する必要は一切ないわけですからね。
自炊代行は違反?合法?
「自分でスキャンするのは大変すぎる…機材もないし、プロにお願いしたい」と考えたとき、候補に挙がるのが「自炊代行サービス」ですよね。これ、実はかなりデリケートな問題で…。
過去に著名な作家さんたちが自炊代行業者を訴えた「自炊代行事件」という裁判がありました。この判決で、司法(最高裁)は代行業者の行為を違法(著作権侵害)と判断しています。理由は大きく2つです。
- 複製の主体は誰か: 依頼したのは本の所有者(顧客)でも、スキャンという「複製行為」を物理的に実行しているのは「代行業者」である。
- 目的は何か: 代行業者は「営利目的」で複製行為を行っている。
この2点から、業者の行為は「私的複製」の要件を満たさない、とされたわけです。
自炊代行の利用は法的にグレー(限りなく黒)
業者の行為が違法と認定されている以上、そこに本を送って依頼する私たち利用者も、その違法行為に関わっていると見なされる法的リスクがあります。
「スキャンピー」さん や「BOOKSCAN」さん など、市場には様々なサービスが今も存在し比較されていますが、こうした司法判断があったという事実は、利用する前に必ず知っておくべきです。
本記事は、これらのサービスの利用を推奨するものではありません。法律に関する最終的な判断や詳細については、弁護士などの専門家にご相談ください。
結論として、現状で100%合法と言い切れるのは、「本人が自分でスキャンする(または家族など手足となる範囲の人が手伝う)」というDIY自炊のみ、ということになりそうです。
ちなみに、参考までに主要な代行サービスを比較した情報も載せておきますが、あくまで情報として、ですね。
| 参考:自炊代行サービス比較 | ||
| 比較項目 | スキャンピー (Scanpy) | BOOKSCAN |
| 基本料金 (税込) | 88円 (300ページまで) | 165円 (350ページまで) |
| カラースキャン (OP) | +55円 | 無料 (基本料金に含む) |
| OCR処理 (OP) | +88円 | +165円 (プレミアム会員は無料) |
| ファイル名変更 (OP) | 無料 | +82.5円 |
| 納期(通常便) | 25日 (100冊まで) | 2~4ヶ月 |
| データ保証期間 | 30日間 | 10日間 |
| 独自サービス | バリューパック(カラー+OCR+ファイル名変更セットで231円) | 特許取得「チューニングラボ」(デバイス別PDF最適化) |
本を裁断せずにPDF化したい時は
「自炊=本を裁断機でバラバラにする」というイメージ、強いですよね 。あのギロチンみたいな裁断機で背表紙を切り落とすのは、かなりの勇気がいります。
私も「お気に入りの本を裁断するのは心理的ハードルが高すぎる…」と思っていました。でも、ご安心ください。今は「非破壊スキャナ」という選択肢があります。
これは、その名の通り本を破壊せず、見開きの状態で上からスキャンできる画期的なスキャナです。
非破壊スキャナ(オーバーヘッドスキャナ)
- メリット: 本を裁断する必要が一切ない。原本をキレイなまま残せる。罪悪感ゼロ。
- デメリット: 1ページずつ手動でめくる必要があるため、スキャンに時間がかかる。本体価格も高めな傾向。
裁断スキャナ(ADFスキャナ)
- メリット: ADF(自動原稿送り装置)で数百枚のページを高速・自動でスキャンできる。両面同時スキャンも可能。
- デメリット: 必ず本を裁断する必要がある 。一度裁断したら元に戻せない。
「CZUR(シーザー)」 や「iCODIS」 などのブランドが有名で、最近のモデルは性能がすごいです。本を開いた時にどうしても発生するページの「歪み(湾曲)」を、AIが認識して自動で平らなページのように補正してくれる機能が付いていたりします。
「本は絶対に切りたくない!」「蔵書としての価値も残したい!」という人は、時間はかかっても非破壊スキャナを選ぶのが、精神衛生上も良いかなと思います。私も今、一番注目している機材です。
kindle自炊のファイル形式と転送
さて、法的な問題をクリアし、スキャン方法(裁断 or 非破壊)も決めたら、いよいよ技術的な話です。スキャンしたデータをどのファイル形式にするか、そしてそれをどうやってKindleに送るか。
この「最後のひと手間」が、快適な自炊ライフを左右しますよ!ここを最適化しないと、「せっかく自炊したのに読みにくい…」なんてことになりかねませんからね。
最適な自炊ファイル形式とは
Kindleで読むためのファイル形式…と聞くと、悩みますよね。Amazon公式が推奨しているのは、文字サイズやレイアウトを自由に変更できる「EPUB」形式です。
これは「リフロー型」と呼ばれ、スマホやKindleなど、画面サイズが違っても自動で読みやすく再配置してくれる、電子書籍に最適化された形式です。…なんですが!
私たちがスキャナで「自炊」して作れるデータは、基本的に「ページの画像を束ねたPDF」です。これは「固定レイアウト」と呼ばれ、見た目は紙の本と全く同じですが、文字サイズの変更などはできません。
この画像PDFを、リフロー型のEPUBに変換するには、単なるファイル変換ではダメなんです。次項で説明するOCR処理をして、さらに文章の構造(章立てや段落、見出し)を全部イチから組み直すという、とんでもなく大変な編集作業が必要になります。
正直、DIYの範囲では現実的じゃないかな…と私は思います。なので、多くの自炊ユーザーにとっての現実的なゴールは、「OCR処理をしたPDF」かなと思います。
「OCR処理済みPDF」とは?
OCR (光学的文字認識) は、画像の中の文字を認識してテキストデータに変換する技術です。「読取革命」 や、スキャナ付属のソフト などを使うと、スキャンしたPDF(ただの画像)の裏側に、透明なテキスト情報を埋め込むことができます。
これにより、Kindle上で見た目はスキャン画像のまま(固定レイアウト)ですが、本文の「全文検索」が可能になります。専門書や技術書、資料集などで「あの単語、どこに書いてあったっけ?」と探すときに、この機能が本当に便利なんですよね。自炊の価値が爆上がりする処理だと私は思っています。
結論、テキストベースの本(小説など)は「EPUB」が理想ですが、あらゆる本に対応できる自炊の現実解としては「OCR処理済みのPDF」が最適解になるかな、と私は考えています。
自炊漫画に多いZIPファイル
小説やビジネス書とは別に、漫画を自炊する人も多いですよね。漫画は基本的に「画像」の集まりです。OCRでテキスト化する必要も(基本的には)ありません。
こうした場合、スキャンした全ページの画像ファイル(JPGなど)を、単純にZIPファイルに圧縮するという方法がよく使われます。
このZIPファイルの拡張子を「.cbz」 (Comic Book Zip) に変更すると、多くの電子書籍リーダーアプリが「これは漫画のファイルだな」と認識して、見開き表示などをサポートしてくれるようになります。
ただ、Kindle自体は直接ZIPやCBZを「Send to Kindle」で受け付けてはくれない(はず…)です。そのため、Kindleで読む場合は、このZIP(画像群)をPDF化するか、「Calibre(キャリバー)」 のような電子書籍管理ソフトを使ってKindleが読める形式(MOBIやEPUB、またはPDF)に変換する、という一手間が必要になりそうです。
表紙をjpgで保存する理由
「Send to Kindle」の対応形式 を見てみると、PDFやWord文書だけでなく、JPEG (.JPG) やPNG、GIFといった画像ファイルもサポートされています。
なぜ画像ファイル?と思うかもしれませんが、これはKindleライブラリの「見た目」に関わってきます。
自炊の効率的なプロセスとして、表紙カバーや帯(カラー)と、本文(白黒やグレースケール)は、スキャン設定を変えて別々にスキャンすることがよくあります。本文はデータ容量を軽くするためにグレースケールのPDFにし、表紙だけは高解像度のキレイなJPG画像として保存しておく。そして、本文PDFとは別に、この表紙JPGもKindleに送る、といった使い方が考えられます。
Kindle端末のライブラリ一覧で見たときに、キレイな表紙が表示されていると、やっぱり気分が上がりますからね。そういった「書斎の見た目」を整えたいというニーズがあるのかもしれません。
旧mobiと新EPUB形式
昔からKindle自炊をしている人にとっては「MOBI」形式がお馴染みでした。Kindle独自の形式で、自炊データもMOBIに変換することが推奨されていた時代もあります。しかし、AmazonはこのMOBI形式のサポートを段階的に終了しています。
リフロー型(文字サイズ変更可)のMOBIは2021年にサポートが終わり、残っていた固定レイアウト(画像ベース)のMOBIについても、2025年3月18日をもって受付を完全に終了すると公式に発表されています(出典:Amazon KDP ヘルプページ )。
代わりに、Amazonは公式に「EPUB」形式を推奨しています。数年前から「Send to Kindle」のEメール転送でもEPUBファイルがサポートされるようになり、Kindleプラットフォーム全体がEPUBに移行している流れですね。
これから自炊データを管理するなら、もうMOBI形式にこだわる理由はなく、基本は「PDF」、もしリフロー化(EPUB化)に挑戦するなら「EPUB」の2択で考えるのが良さそうです。
自炊本の入れ方の手順
さあ、いよいよ最後のステップ!完成した自炊ファイル(PDFやEPUBなど)をKindle端末に入れる方法です。主な方法は3つあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
方法1:Eメール (Send-to-Kindle) で送る
これが一番手軽で、Amazonのクラウド(Kindleライブラリ)に同期されるので、私がメインで使っているおすすめの方法です。
Kindle端末ごとに割り当てられた専用のメールアドレス(xxxx@kindle.com みたいなアドレス)宛に、自炊ファイルを添付して送るだけです。
この方法には一つ、有名な「ワナ」があります。
件名「変換」のワナ
Eメールの件名に「変換」と入力して送ると、Amazon側が添付ファイルをKindleの独自形式(AZW)に自動変換しようとしてくれます。
しかし! 自炊したPDF(特にレイアウトが凝ったものや漫画)を変換させると、レイアウトがぐちゃぐちゃになる可能性が非常に高いです。PDFはPDFのまま(固定レイアウトのまま)読みたいので、件名は「空欄」で送るのがおすすめです。
方法2:PCからUSBケーブルで直接転送する
PCとKindle端末をUSBケーブルで物理的に接続して、データを手動でコピーする方法です。
- PCとKindleをUSBケーブルで接続します。
- PCがKindleを外部ストレージ(USBメモリのようなもの)として認識するのを待ちます。
- PCのエクスプローラー(やFinder)でKindleドライブを開き、「Document」という名前のフォルダを探します。
- 自炊ファイル(PDFなど)を、その「Document」フォルダにドラッグ&ドロップでコピーします。
- PC側で「安全な取り外し」操作をしてから、ケーブルを抜けば完了です。
この方法の最大のメリットは、大容量のファイルでも高速に転送できることです。一方、最大のデメリットは、クラウド同期されないこと。つまり、転送したその端末でしか読めません。
他のスマホやタブレットのKindleアプリと同期したい場合は、方法1(Eメール)を選びましょう。
方法3:スマホのKindleアプリから送る
PCを使わずに、スマホから直接クラウドにアップロードする方法です。これも非常に便利で、次の項目で詳しく説明しますね。
転送に便利な自炊 アプリ
上で紹介した3つの方法のうち、Eメール(方法1)とUSB(方法2)の中間的な便利さなのが、スマホのKindleアプリ(iOS/Android)を経由する方法です。
これは「Send to Kindle」機能のアプリ版、と言うと分かりやすいかもしれません。PCで作成した自炊PDFを、一旦Google DriveやDropbox、iCloudなどのクラウドストレージに入れておけば、あとはスマホ操作だけで完結します。
手順はこんな感じです(使っているアプリによって多少文言が違います )。
- スマホで「Google Drive」や「ファイル」アプリを開き、転送したい自炊PDFファイルを選びます。
- 「共有」や「コピーを送信」メニューを選択します。(※AndroidのGoogle Driveの場合、「アプリで開く」を選ぶと転送されず、ただスマホのアプリで開くだけになるので注意です )
- 共有先アプリアイコンの中から「Kindle」を選びます。
- タイトルや著者名を入力する画面が出るので、入力(またはそのまま)にして「送信」をタップ。
これだけです。すごく簡単ですよね。
この時、「Kindleライブラリに保存」にチェックを入れておけば 、Eメール転送(方法1)と全く同じようにAmazonのクラウドに保存され、あなたが持っている他のすべての端末(Kindle本体や他のスマホ、PCアプリ)とも自動的に同期されます。
PCを起動するのが面倒な時や、出先で「あ、あのPDFをKindleに入れておこう」と思い立った時に、すごく便利な方法ですね。
快適なkindle 自炊のために
いやー、Kindle自炊、調べてみると本当に奥が深いです。技術的な側面だけでなく、法的な側面もしっかり理解しておかないといけない、ちょっとハードルの高いDIYだなと改めて感じました。「自炊」と一口に言っても、クリアすべき課題は多いです。
自炊のデメリットとコスト
- 法的リスク: 自炊代行サービスの利用は、司法判断で「違法」とされています。安全なのはDIYのみです。
- 初期費用: 裁断機やドキュメントスキャナ(または非破壊スキャナ)を揃えるのに、数万円のコストがかかります。
- 時間と手間: スキャン作業、傾き補正 、OCR処理 、ファイル管理など、膨大な作業時間(機会費用)がかかります。
- 資産価値の喪失: 裁断方式の場合、本は物理的に破壊され、古本としての資産価値はゼロになります。
- データ喪失リスク: デジタルデータはHDDの故障やクラウドサービス停止で一瞬にして全てを失う可能性があります。バックアップが必須です。
その一方で、これらのコストを払ってでも手に入れたい、強力なメリットがあるのも事実です。
自炊の強力なメリット
- 物理スペースの解放: 部屋を圧迫していた本棚が不要になり、空間が解放されます。
- 携帯性の最大化: 何千冊もの蔵書をKindleデバイス一台に集約し、書斎ごと持ち運べます。
- 検索性の獲得: これが最大の価値かも。OCR処理 により、蔵書が「全文検索可能なデータベース」に変貌します。
- ライブラリの一元管理: 購入した電子書籍も、自炊した本も、Kindleライブラリでシームレスに一元管理できます。
この記事で紹介したような法的リスクや手間を許容できるか、自分の蔵書量や読書スタイルと見合っているか、一度じっくり考えてみるのが良さそうです。
私自身も、まずは裁断しなくてもいい「非破壊スキャナ」 の導入から、スローペースで自炊ライフを始めてみようかな、なんて考えています。皆さんも、ご自身のスタイルに合った快適な読書ライフを見つけてくださいね。
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません