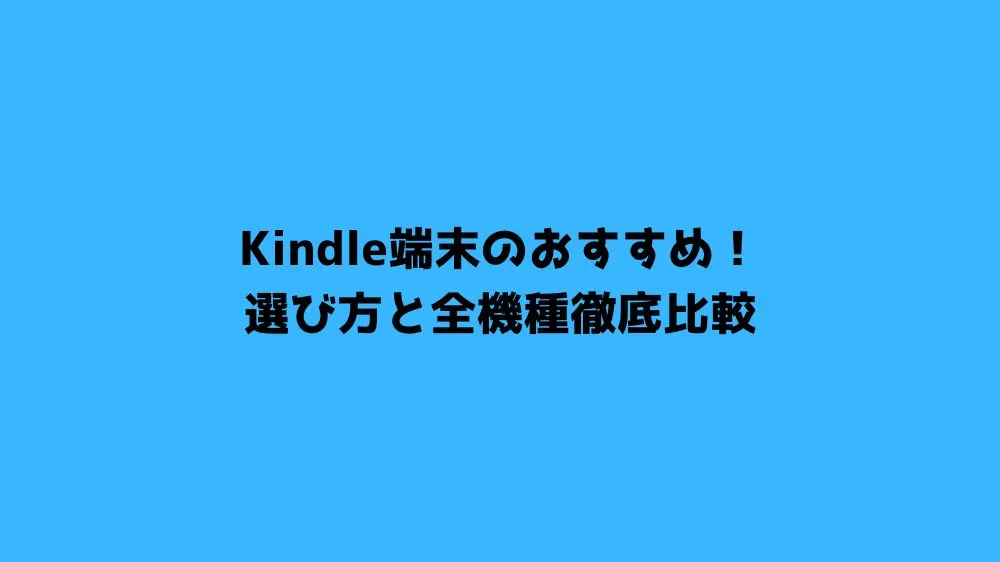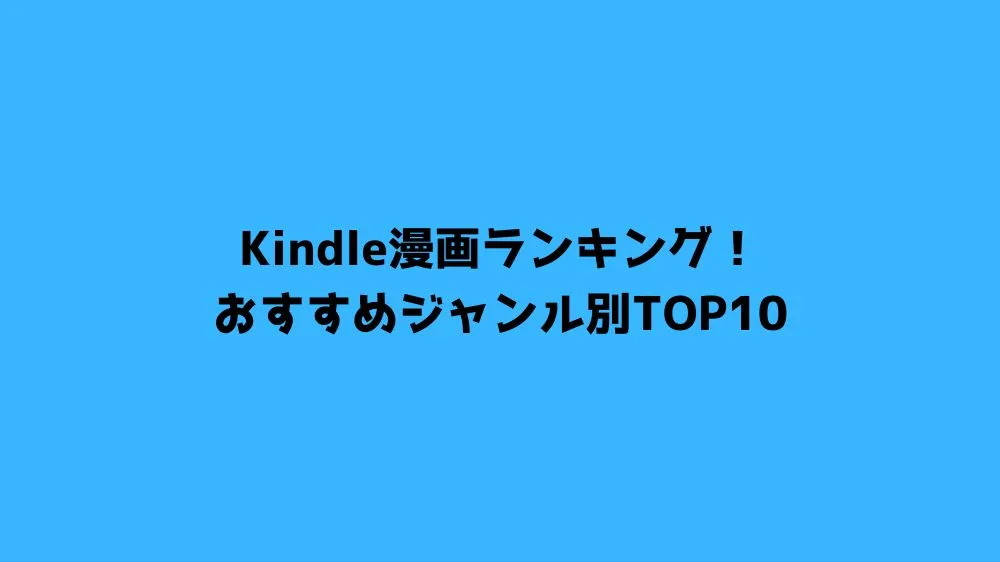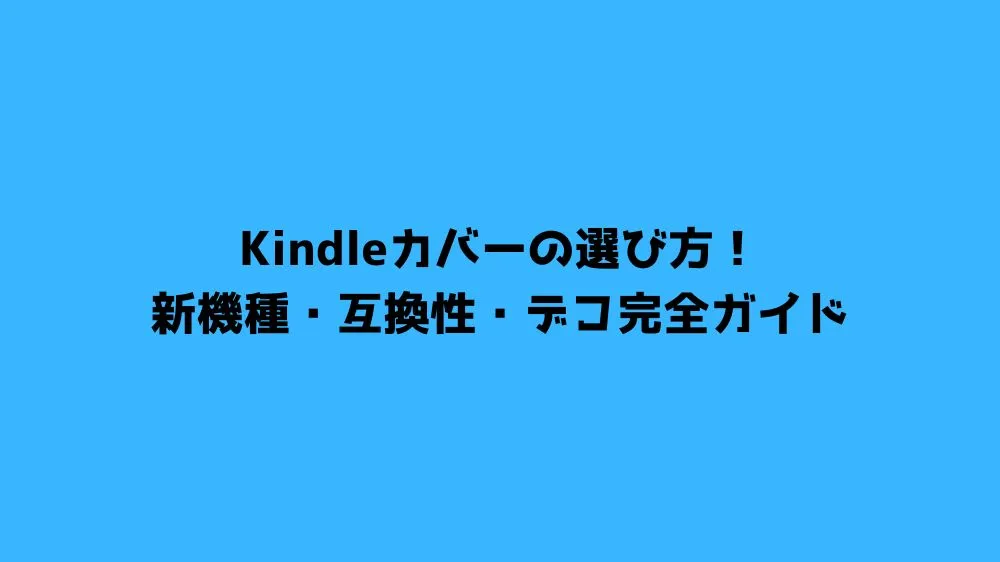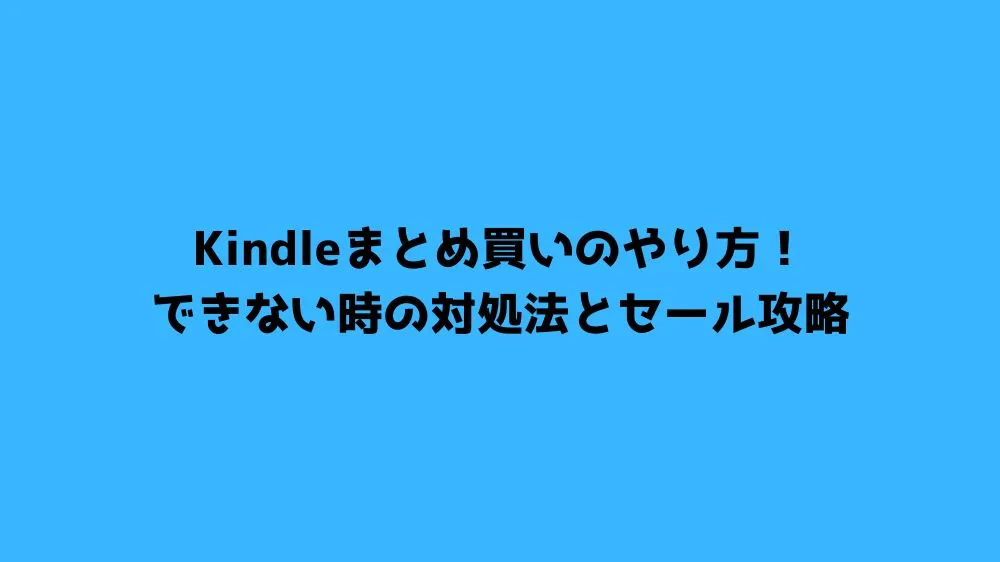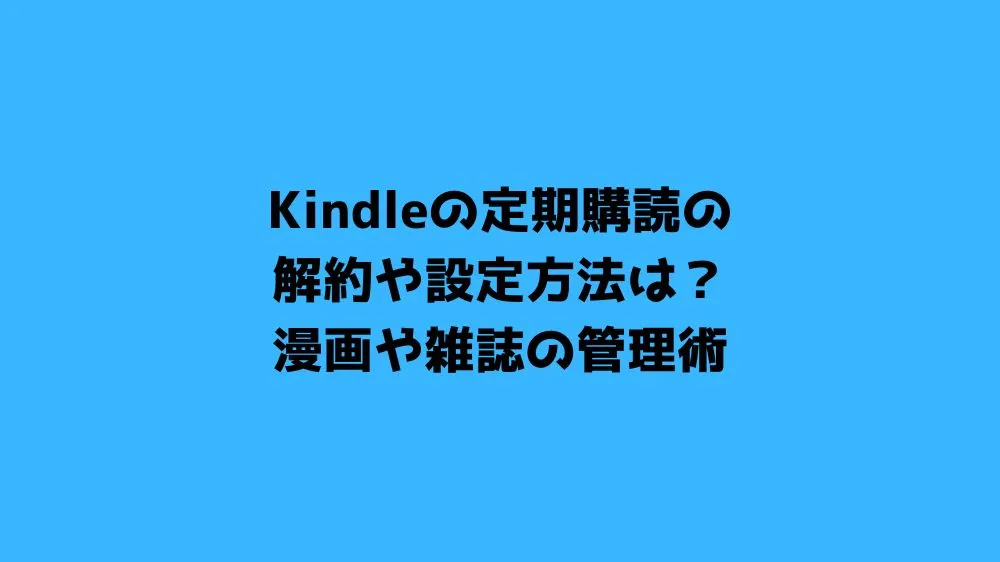読書専用の「kindle デバイス」が気になっている方、結構多いんじゃないでしょうか。私自身、読書が好きなので、その気持ちすごく分かります。
ただ、いざ選ぶとなると「結局どれがいいの?」って迷いますよね。定番のPaperwhiteがおすすめと聞くけど、Scribeの手書き機能も気になるし、最近出たColorsoftでの漫画体験も捨てがたい…。
それに、kindle デバイスの比較だけでなく、購入時の「広告ありなしの違い」や、お得な「買い時」であるセールの情報も知っておきたいところです。
この記事では、そんな悩みや疑問をまるっと解決します。各モデルの比較から、購入後の簡単な初期設定の方法、知っていると便利な辞書機能やハイライト、メモ機能の基本的な使い方、さらにはフォントの変更方法やコレクション機能での整理術まで、幅広くカバーしていきます。
あなたにピッタリの一台を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません
本記事の内容
- 現行Kindleデバイス全モデルの徹底比較
- 「広告あり/なし」やストレージ容量の選び方
- 購入後に役立つ初期設定と便利な使い方
- プライムデーなどのお得なセールの買い時
本ページの情報は2025年11月時点の情報です。最新の配信情報は配信サイトにてご確認ください。
初めてのkindleデバイス選び方
Kindleデバイスと一口に言っても、今はたくさんのモデルがラインナップされています。ここでは、2025年現在のモデルを比較しながら、あなたにピッタリの一台を見つけるためのポイントを解説していきますね。
現行kindle デバイスの徹底比較
2025年現在、Amazonから公式に発表されている主な現行モデルは、かなり個性豊かになりましたね(笑)。
昔は「Kindle(無印)」と「Kindle Paperwhite」の2択で分かりやすかったんですが、今は手書きができる「Scribe」 や、ついにカラー表示に対応した「Colorsoft」 も加わり、選択肢がぐっと広がりました。
まずは、全モデルの主要な違いを一覧表にまとめてみます。こうやって並べると、それぞれの得意分野が見えてきますよ。
| モデル名 | 画面 | ストレージ | 防水 | 明るさ自動調節 | ワイヤレス充電 |
| Kindle (無印) | 6インチ | 16GB | なし | なし | なし |
| Kindle Paperwhite | 6.8インチ | 16GB | あり (IPX8) | なし | なし |
| Paperwhite シグニチャー | 6.8インチ | 32GB | あり (IPX8) | あり | あり |
| Kindle Colorsoft | 7インチ | 16GB | あり (IPX8) | なし | なし |
| Colorsoft シグニチャー | 7インチ | 32GB | あり (IPX8) | あり | あり |
| Kindle Scribe | 10.2インチ | 16/32/64GB | なし | あり | なし |
この比較表での大きな分岐点は、「防水機能」と「色調調節ライト」の有無かなと思います。この2つが搭載されるのが「Kindle Paperwhite」以上のモデルなんです。
ベーシックな「Kindle (無印)」も、2022年以降のモデルで解像度が300ppiに統一され 、文字がすごく読みやすくなったんですが、防水とお風呂での読書を考えるならPaperwhite以上が必要になる、という感じですね。(出典:Amazon Japan「Kindle(キンドル)電子書籍リーダーの比較と選び方」)
【余談】物理ボタン搭載の「Oasis」は販売終了
ちなみに、以前は「Kindle Oasis」という、人間工学に基づいたグリップと「物理的なページめくりボタン」を搭載した高級モデルがありました 。あれはあれで、片手での操作感が最高だったんですが、残念ながら現在は生産・販売が終了しています。
Amazonの戦略が、「紙の操作感の再現」から「手書き(Scribe)」や「カラー(Colorsoft)」といったデジタルならではの付加価値へとシフトした感じがしますね。物理ボタン派だった方には残念なお知らせですが、現在はこれが公式ラインナップとなります。
Paperwhiteはこんな人におすすめ
もし「色々ありすぎて分からない!一番間違いないモデルは?」と聞かれたら、私はKindle Paperwhiteを推しますね。
理由は、機能と価格のバランスが最も取れている、まさに「優等生」なモデルだからです。
- 6.8インチの画面:無印の6インチ よりも一回り大きく、この0.8インチの差が結構大きいんです。小説はもちろん、漫画を読むときもセリフやコマ割りが読みやすくなる、絶妙なサイズ感ですね 。
- IPX8等級の防水機能:これがお風呂読書派には必須の機能です 。IPX8等級というのは、「真水で水深2メートルまで最大60分耐えられる」という結構しっかりした防水性能 。これなら、うっかり湯船に落としても慌てなくて済みます。キッチンなど水回りで読書する方にも安心ですね。
- 色調調節ライト:画面の色を、白い光から暖色系(オレンジっぽい光)まで自由に調節できる機能です 。特に夜、寝る前に読書をするとき、この暖色系の光が目に優しくて重宝します。ブルーライトを直接カットするわけではないですが、体感としてリラックスして読書に入り込めますよ。
「無印」にはない、これらの「あると嬉しい機能」が全部入りで、価格は「Scribe」や「Colorsoft」といった上位モデルよりずっと安い。まさに「迷ったらコレ」と言える、Amazonの売れ筋モデルです 。
Paperwhiteがおすすめな人
- お風呂やキッチンなど水回りで読書したい人
- 小説も漫画も、バランスよく快適に読みたい人
- 寝る前に目に優しいライトで読みたい人
ちなみに、さらに上位の「シグニチャーエディション」を選ぶと、どうなるかも気になりますよね。違いは主に3つです。
- ストレージが32GBに倍増(通常モデルは16GB)
- 明るさ自動調節機能(周囲の明るさに合わせてライトを自動調整)
- ワイヤレス充電(Qi)に対応
価格差は5,000円ほど なので、漫画やPDFをデバイスに大量に保存しておきたい人(32GBは魅力です)や、ケーブルの抜き差しすら面倒!という人 、常に最適な明るさで読みたい人には、シグニチャーエディションも良い選択肢になるかなと思います。
Scribeの手書き機能と活用法
Kindle Scribeは、他のモデルとはちょっと毛色が違いますね。これはもう「読む」と「書く」を融合させた別カテゴリのデバイスです。最大の特徴は、なんといっても10.2インチのKindle史上最大の画面と「手書き機能」です。
付属の専用ペン(嬉しいことに充電もペアリングも不要!) で、紙のノートのようにスラスラと書き込めます。主な使い方はこんな感じです。
付属の専用ペンの使い方
- Kindle本への「付箋メモ」: 本文に直接書き込むのではなく、本を読みながら付箋を貼る感覚で手書きメモを残せます。
- PDFへの直接書き込み: これが強力で、PCなどから転送したPDF文書に、直接赤入れをしたり、サインをしたり、注釈を書き込んだりできます。
- ノート機能: ToDoリストや会議の議事録、授業のノートなどを取るための専用ノート機能も搭載されています。
特にPDFへの書き込みは便利で、仕事の資料をチェックしたり、学生さんが論文を読んだりするのにも使えます。
ペンの違いに注意してください
Scribeには「スタンダードペン」と「プレミアムペン」付属モデルがあります。
プレミアムペンには、ペンの反対側に消しゴム機能が、側面にはカスタマイズ可能なショートカットボタン(マーカーや付箋機能などに設定可能)が搭載されています。スタンダードペンにはこれがありません。
この差は結構大きいと私は思います。メモを取っていて、間違えたときにサッとペンをひっくり返して消せる のは、紙のノートと鉛筆(消しゴム付き)の感覚に近くて、思考を妨げません。予算が許せば、個人的にはプレミアムペン付きが断然おすすめですね。
大画面なので、漫画を見開きのように楽しみたい人 や、勉強用のガジェットを探している人にも面白い選択肢になると思います。
Colorsoftで漫画や雑誌を読む
2025年に登場した待望のカラーモデルが「Kindle Colorsoft」です。
これでついに、KindleのE-inkディスプレイ(電子ペーパー)で、漫画のカラーページや雑誌の表紙、図鑑などが色付きで読めるようになりました。サイズは7インチ 、Paperwhite同様のIPX8防水機能も付いています。
ただ、この「カラー」については、購入前に知っておくべき重要な注意点があります。
まず大前提として、タブレット(iPadやFireタブレット)の液晶画面のような、鮮やかでクッキリした発色を期待してはいけません。
ColorsoftはあくまでE-ink(電子ペーパー)のカラー版(Kaleido 3)です。そのため、以下のような技術的な特性(トレードオフ)があります。
- カラー解像度は低め: 白黒の文字は300ppiでクッキリですが、カラー表示は150ppi となります。
- 発色は地味: 液晶と比べると、全体的に「淡く」「地味(dull)」な色合いだと評されることが多いです。
- 画面が少し暗い: カラーフィルター層が追加された影響で、従来の白黒モデル(Paperwhiteなど)と比べると、画面がわずかに暗く感じる場合があります。
- 操作時のちらつき: E-inkの特性上、特にカラー表示でのズームやスクロール(漫画を拡大する時など)は、画面のちらつき(ゴースト)が発生しやすいです。
このモデルの「カラー」は、タブレットで写真や動画を「鑑賞」するためのものではありません。あくまで、雑誌の表紙、図鑑、漫画のカラーページ、または書籍のハイライト(マーカー)を「色分けして識別する」ための機能、と考えるのが良さそうです。
とはいえ、Kindleの「目の疲れにくさ」や「圧倒的なバッテリー持ち」といったメリットはそのままに 、カラーが手に入ったのは大きな進化です。漫画や雑誌を読む比率が高い人には、新しい選択肢になりますね。
こちらもPaperwhite同様に「シグニチャーエディション」があり、ストレージが32GBに増え、ワイヤレス充電と明るさ自動調節機能が追加されます 。カラーの漫画や雑誌を大量に保存したい人は、こちらを検討するのが良いと思います。
広告ありなしの違いと選び方
Kindleを選ぶ時、多くのモデルで(シグニチャーエディションやScribe以外で)「広告あり」か「広告なし」かを選ぶことになります。これは結構迷うポイントですよね。結論から言うと、「広告あり」モデルは「広告なし」より2,000円安く買えます。
では、その2,000円の差はどこに出るのか? 広告が表示される場所は、以下の2箇所だけです。
- スリープ(ロック)画面電源をオフ(スリープ)にしている時の画面が、Amazonのおすすめの本などの広告に置き換わります。スリープを解除するには、この広告画面を一度スワイプする必要があります。「広告なし」モデルの場合は、おしゃれな画像が表示され 、スワイプなしでホーム画面に移れます(電源ボタンを押すだけで復帰)。
- ホーム画面の最下部ホーム画面(本棚)の一番下、ライブラリとは別の領域に、小さなバナー広告が表示されます。これはスクロールしないと目に入らない場所なので、個人的にはほとんど気にならないレベルかなと思います。

つまり、この2,000円の差は、ほぼ「スリープ解除時に広告を見たくないか、スワイプの手間をどう考えるか」だけなんですね。「少しでも安く買いたい」「ロック画面の広告は別に気にならない」という人は、「広告あり」モデルで全く問題ないと思います。
逆に、「2,000円高くても、スリープ画面は広告じゃない方がいい」「スワイプの手間なく、すぐに読書を再開したい」という人は「広告なし」を選ぶと、日々の小さなストレスがなく満足度が高いです 。私は後者なので「広告なし」を選びがちですね。
もっと活用!kindleデバイス術
無事にKindleデバイスを手に入れたら、次は活用あるのみです。読書体験をもっと快適にするための、基本的な設定や便利な機能を紹介しますね。これを知っているだけで、読書効率がぐっと上がりますよ。
簡単な初期設定の方法
Kindleデバイスが届いたら、まずは初期設定(セットアップ)です。と言っても、全然難しくありません。基本的には画面の指示に従うだけなので、PCやスマホの設定に慣れていない方でも大丈夫です。
初期設定の主な流れ
- 電源オンと言語選択まずは電源を入れます。最初に「使用する言語」を聞かれるので、[日本語] を選択して[開始]をタップします 。
- Wi-Fiに接続次にWi-Fiへの接続設定です。自宅のWi-Fiネットワーク(SSID)を選んで、パスワードを入力して [接続] します 。KindleはWi-Fiがないと本をダウンロードできないので、ここは必須のステップです。
- Amazonアカウントを登録これが一番重要です。Kindleデバイスは、あなたのAmazonアカウントと紐づいて機能します。普段お買い物をしているAmazonアカウントのメールアドレス(または電話番号)とパスワードを入力して[登録]をタップします 。
- (任意)その他の設定最後に、ワンクリック支払い方法の設定 や、ソーシャルネットワーク(X/Twitterなど)との連携 を聞かれることがありますが、これらは「後で」を選択してスキップ可能です。後からでもいつでも設定できます。
- 設定完了![続行]をタップすれば初期設定は完了です 。ログインしたアカウントで過去に購入したKindle本 が、自動的にライブラリに同期され始めます。
使い方:便利な辞書機能
Kindleデバイスを使っていて、私が個人的に「これ、便利!」と一番実感するのが内蔵辞書機能です。小説やビジネス書を読んでいると、「この言葉、どういう意味だっけ?」とか「この漢字、なんて読むんだっけ?」と流れが止まってしまうこと、ありますよね。
Kindleなら、そのわからない単語を指で長押しするだけ。それだけで、画面下に辞書がポップアップして「大辞泉」などの辞書が瞬時に意味を表示してくれます。スマホで別途検索する手間が一切ないので、読書の流れを止めずに意味をすぐ確認できるんです。
標準で「大辞泉」や「プログレッシブ英和中辞典」など、国語辞書も英和・和英辞書も入っているので、特別な設定は不要ですぐに使えます。
この機能は、特に洋書(英語の本)を読むときに大活躍します。わからない英単語を長押しすれば、すぐに英和辞書で意味が出てきます。いちいち紙の辞書を引いたり、別のアプリを立ち上げたりする必要がありません。
さらに、洋書には「WordWise(ワードワイズ)」という機能が対応している本も多いです。これは、本文中の難しい英単語の上に、簡単な類義語(英語)を自動で表示してくれる機能。
これのおかげで、辞書を引く回数すら減り、英語の多読がすごくはかどります。英語学習者には本当にピッタリな機能ですね。
ちなみに、Amazonのアカウントサービス(コンテンツと端末の管理)から、スペイン語辞書 などを追加でダウンロードしたり、Kindleストアで辞書ファイル(mobi形式)を購入して追加 したりと、カスタマイズも可能です。
ハイライトとメモ機能の活用法
紙の本にマーカーを引いたり、気になったページの端を折ったり(ドッグイヤー)、メモを書き込んだりしますよね。Kindleでももちろん、それに近い「ハイライト」と「メモ」機能が使えます。しかも、紙よりずっと管理が楽なんです。
ハイライトとメモの付け方
使い方は辞書機能とほぼ同じ。気になった文章、残しておきたいフレーズを指で長押しして、そのままスーッとドラッグするだけ 。これでハイライト(マーカー)が引けます。
ハイライトした箇所をもう一度タップすれば、メニューが出てきて「メモ」を選ぶと、キーボードで自分の考えやメモを書き込むことも可能です。
付けたハイライトを見返す方法
「あのハイライト、どこだっけ?」と、後から見返したくなった時の方法が秀逸です。
- 読書中に、画面の上の方をタップしてメニューバーを表示させます。
- メニューにある「ノート」のアイコン(または「移動」→「注釈」)をタップします。
たったこれだけで「注釈」画面が開いて、その本の中で自分が付けたハイライトやメモが、一覧でズラッと表示されます 。
一覧から読みたい箇所をタップすれば、本文のそのページに一瞬でジャンプできる ので、読書ノート代わりにもなってすごく便利です。紙の本だと、マーカーを引いた場所を探してパラパラめくる必要がありますが、Kindleなら一瞬ですね。
その他の活用法
ちなみに、ハイライトした箇所をタップすれば、ハイライトの範囲を修正したり、[×]ボタンで削除したりすることも簡単にできますよ。
また、AmazonアカウントとX (Twitter) などのSNSを連携設定しておけば、ハイライトした箇所を引用し、コメントを付けて投稿(シェア)することも可能です 。
フォントを変更する方法
「なんだか文字が読みにくいな…」「もう少し文字を大きくしたい」と感じたら、フォント(書体)や文字サイズを自由に変更できます。自分にとって一番読みやすい設定にカスタマイズできるのも、電子書籍の大きなメリットですね。
変更方法はとっても簡単です。
- 読書中に、画面の上の方をタップしてメニューを表示させます。
- メニューの中央あたりにある[Aa]というアイコンをタップします。
- [フォント] というタブを開くと、設定項目が出てきます。
ここで、以下の項目を自由に変更できます。
- フォントの種類: 「筑紫明朝」や「ゴシック体」など、複数の日本語フォントから選べます。小説なら明朝体、ビジネス書ならゴシック体など、気分や本の種類で変えてみるのも面白いですよ。
- 文字の太さ: スライダーで文字の太さを細かく調整できます。太くすると、コントラストがはっきりして読みやすくなる場合があります。
- 文字のサイズ: 14段階以上、かなり細かくサイズを選べます。自分の一番楽なサイズに設定しましょう。
自分好みの設定を見つけると、長時間の読書でも疲れにくくなり、格段に快適になりますよ。ちなみに、PCを持っている上級者向けですが、Kindleは標準フォント以外にも、ユーザーが独自に追加したフォントをサポートしています。
オンラインで配布されているお気に入りのフォントファイル(TTF形式やOTF形式など )をダウンロードし、PC経由でKindle端末の指定フォルダに転送することで、読書用フォントとして選択できるようになります。
こだわりのフォントで読書したい方は、試してみる価値があるかもしれません。
コレクション機能での整理術
Kindleライフが充実してくると、必ずぶつかるのが「本棚(ライブラリ)がごちゃごちゃ問題」です(笑)。購入した本が数百冊、数千冊と増えてくると、ホーム画面のライブラリがすごいことになってきます。「あの本どこいったっけ?」と探すのが大変になりますよね。
そんな時に絶対に使ってほしいのが「コレクション」機能です。これは、PCの「フォルダ」と同じようなもので、本をカテゴリ分けしてスッキリ整理できます。
使い方は、ホーム画面(ライブラリ)の左上にあるフィルターアイコン(三本線)をタップし、[コレクション] を選択します 。
そこで「読了済み」「積読(つんどく)」「ビジネス書」「お気に入り漫画」「仕事関連資料」といった新しいコレクション(フォルダ)を自由に作成し、そこに本を分類していくだけです。
ライブラリがスッキリ整理されると、読みたい本がすぐに見つかって本当に快適ですよ。本が増えてきたな、と感じたらぜひ試してみてください。
もしコレクションを作ったのにうまく表示されない場合は、[設定] → [デバイスオプション] → [ホームとライブラリ] → [コレクション] へ進み、「ライブラリですべて表示」などの表示オプションが正しく選択されているか確認してみてくださいね 。
お得な買い時はセールを狙おう
さて、買うモデルが決まったとして、一番大事なのが「いつ買うか」です。
結論から言うと、Kindleデバイスは絶対にAmazonの大型セールの時に買うべきです。定価で買うのは本当にもったいないです! Amazonデバイスは、セールのためにあると言っても過言ではないかもしれません(笑)。
Kindleデバイスが大幅に安くなる主なセールは、だいたい決まっています。
過去の実績を見ると、セールのインパクトは絶大です。例えば、売れ筋のKindle Paperwhiteが、プライムデーで7,000円オフになったり 、ブラックフライデーで5,000円オフになったり した実績があります。
最上位モデルのKindle Scribeが、セールで10,000円以上値引きされた例もあるほどです。
最近、Kindleデバイスの定価は上昇傾向にありますが、それに伴ってセール時の割引額も大きくなっている傾向があります。
急いで今すぐ必要!という理由がなければ、「プライムデー」か「ブラックフライデー」のどちらかの大型セールを待って購入するのが、最も賢い買い方だと私は断言します。
セール価格や時期は、当然ながら年によって変動します。この記事で紹介しているのはあくまで過去の実績や目安です。実際の購入時には、ご自身で必ずAmazon公式サイトで最新の価格やセール情報を確認してくださいね。
最適なkindle デバイスを見つけよう
ここまで、Kindleデバイスの選び方から、基本的な使い方、そして一番お得な買い時まで、幅広く紹介してきました。
読書に特化した「kindle デバイス」は、スマホやタブレットとは全く違う読書体験を提供してくれます。通知に邪魔されず 、E-inkの目に優しい画面で 、紙の本を読むように没入できる。一台持っていると、本当に読書がはかどりますし、楽しくなりますよ。
万能な「Paperwhite」を選ぶもよし、「Scribe」で手書きという新しい読書体験 に踏み出すもよし、「Colorsoft」で漫画や雑誌のカラーを楽しむ もよし。あなたの読書スタイルに合ったモデルが、きっと見つかるはずです。
この記事で紹介した辞書やハイライトなどの便利な機能も使いこなしつつ、ぜひお得なセールを狙って、あなたに最適な一台を手に入れてください。この記事が、あなたのkindle デバイス選びの参考になれば幸いです。快適な読書ライフを!
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません