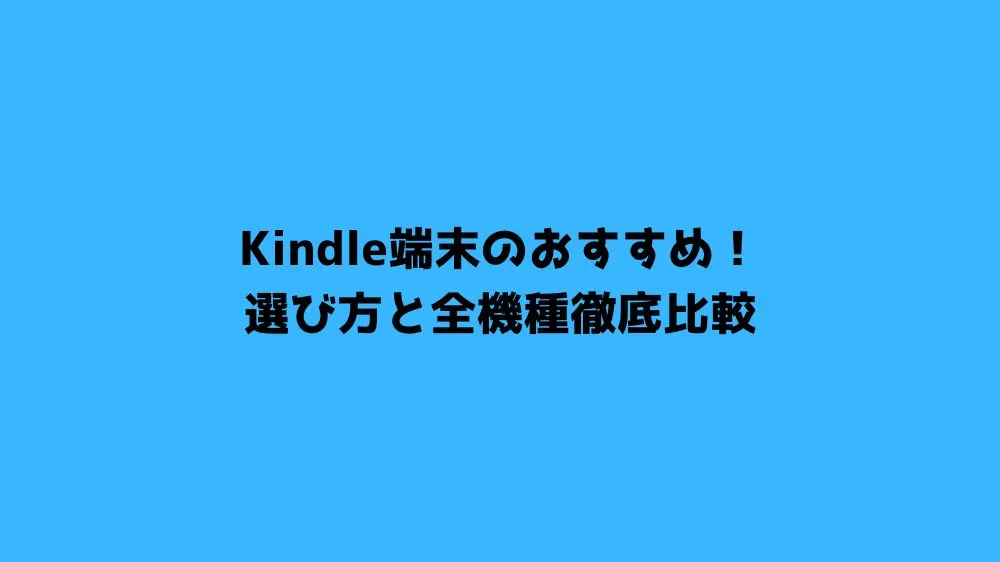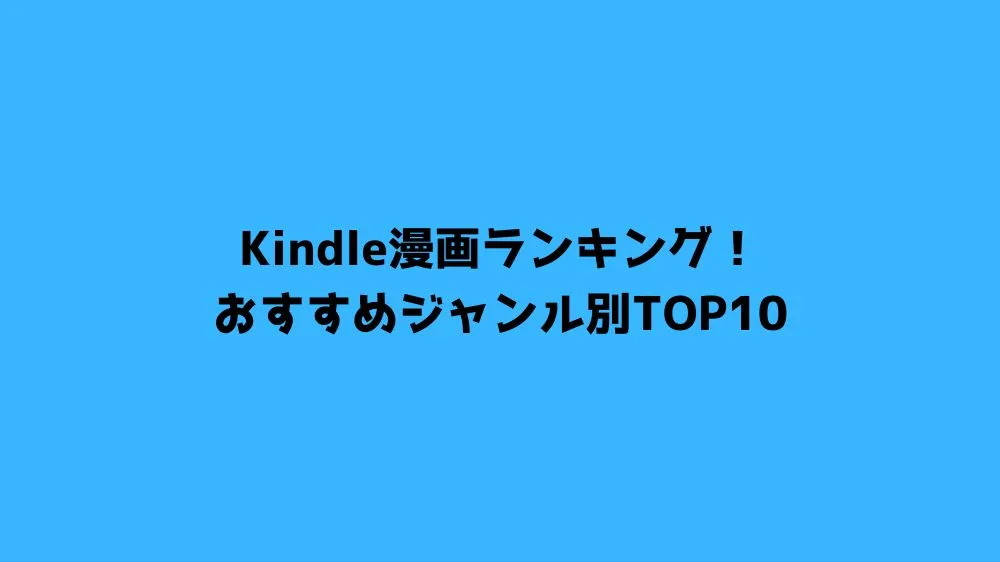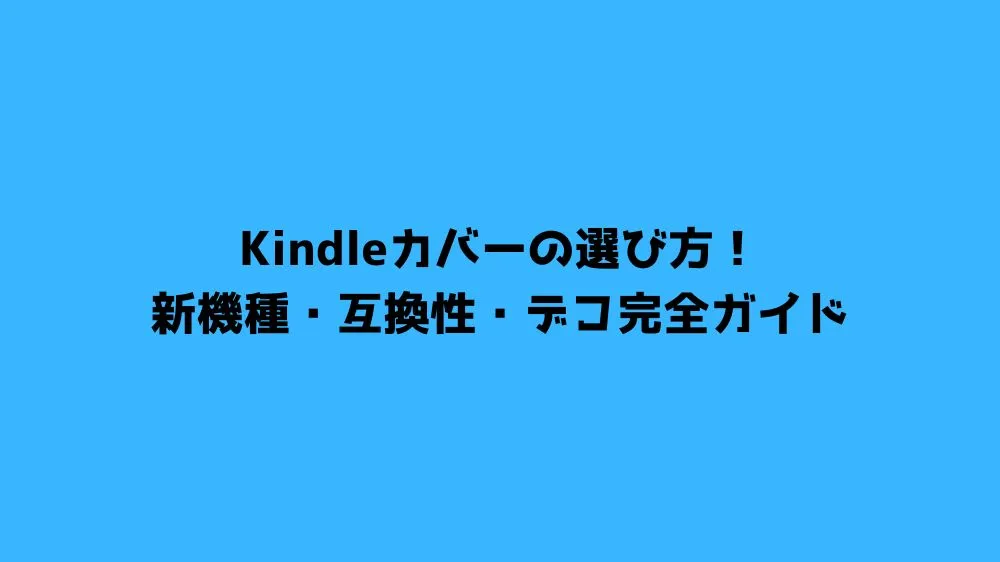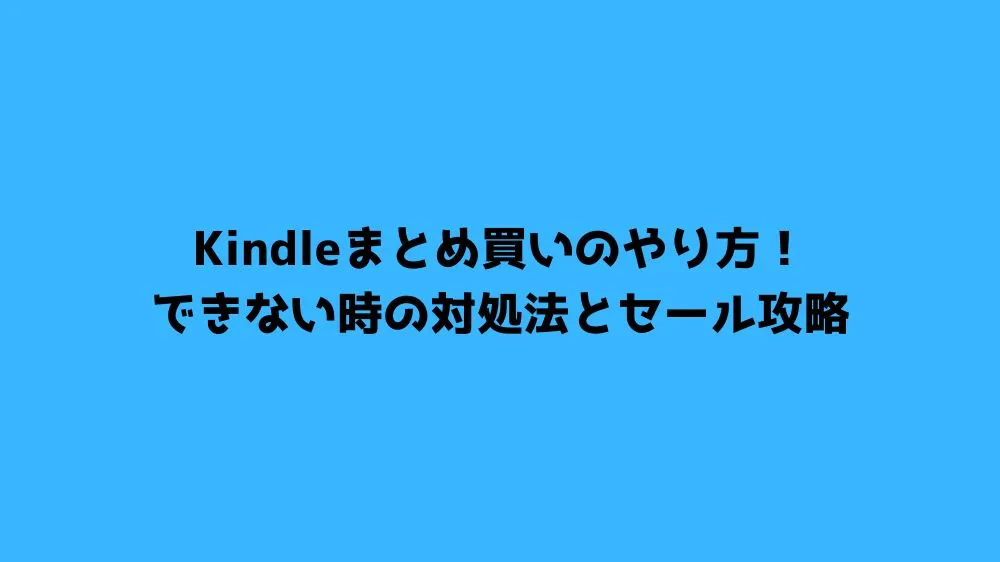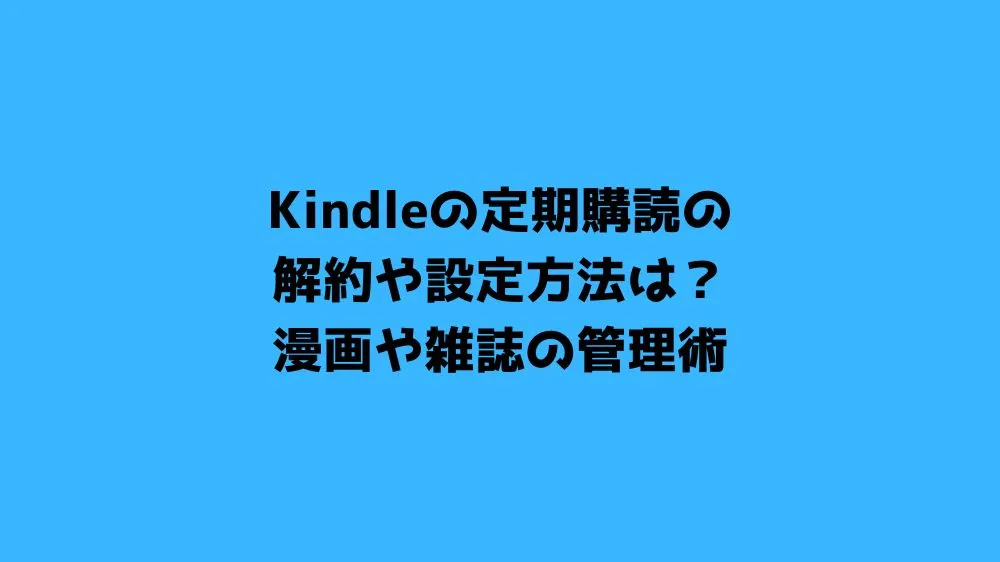kindleのデメリットというキーワードで検索されたあなたは、Kindleの導入を検討中か、あるいは「kindleを買うか迷う」と悩んでいるかもしれません。
「Kindleの何がそんなにいいの?」という評判の裏で、「kindleアプリはゴミ」といった厳しい意見や「kindleは使いにくくなった」という声も実際に存在します。
「kindle端末はいらない」のではと感じる理由や、「Kindleは目が疲れる?」といった具体的な疑問、さらには「Kindleで購入した本はずっと読める?」という将来的な不安や万が一のサービス終了に関する懸念まで、利用者が抱えるメリット デメリットは多岐にわたります。
この記事では、kindleとは何か、料金や使い方といった基本情報から、利用者が直面しがちなデメリットまで詳しく解説します。
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません
本記事の内容
- Kindleの基本サービスと料金体系
- 利用者が感じる具体的なデメリットとその理由
- 専用端末の必要性とスマホアプリとの比較
- サービス終了など将来的なリスクと対策
本ページの情報は2025年10月時点の情報です。最新の配信情報は配信サイトにてご確認ください。
Kindleの概要と主なデメリット
ポイント
- kindleとは?料金や使い方を解説
- Kindleの何がそんなにいいの?
- 検討材料となるメリットとデメリット
- kindleを買うか迷う?判断基準
- kindle端末はいらないという意見も
kindleとは?料金や使い方を解説
Kindle(キンドル)とは、Amazonが提供する電子書籍サービスの総称です。紙の本の代わりにデジタルデータで読書を楽しむための仕組み全体を指します。
これには、電子書籍ストア、スマートフォンやタブレットで読むための「Kindleアプリ」、そして読書専用に設計された「Kindle端末」の3つが含まれます。
利用者がKindleで本を読む際の料金体系は、大きく分けて「1冊ずつ購入する」方法と、「定額で読み放題になる」方法の2種類が存在します。
単品購入
Amazon.co.jpのKindleストアで、読みたい本を1冊ずつ電子書籍として購入する方法です。価格は紙の書籍と比較して同等か、やや割安に設定されているケースが多く見られます。
一度購入手続きを完了すれば、Amazonのアカウントに購入履歴が紐付き、サービスが継続する限りは無期限でダウンロードして読むことが可能です。
読み放題サービス
月額または年額の固定料金を支払うことで、サービス対象に含まれる膨大なラインナップの電子書籍が、追加料金なしで読み放題になるサブスクリプションサービスです。
Amazonは現在、2つの異なる読み放題プランを提供しており、利用者の読書量やニーズによって選択できます。
| サービス名 | 月額料金(税込) | 対象冊数 | 主な特徴 |
| Kindle Unlimited | 980円 | 200万冊以上 | 小説、ビジネス書、実用書、漫画、雑誌、洋書まで、非常に幅広いジャンルが読み放題の対象です。月に2〜3冊以上読む読書家向けの本格的なサービスと言えます。 |
| Prime Reading | プライム会員費に含む (月額600円または年額5,900円。Amazonプライム公式サイト参照) | 1,000冊以上 | Amazonプライム会員(送料無料やお急ぎ便、Prime Videoなどが利用できる会員)の特典の一つです。対象冊数は限定的ですが、追加料金なしで利用できる手軽さが魅力です。 |
Kindleの基本的な使い方
・購入:読みたい本は、Amazonのウェブサイト(PCやスマホのブラウザ)またはKindle専用端末から探して購入手続きを行います。(注意:iPhoneやiPadのKindleアプリ内からは直接購入できません)
・閲覧:購入した本は、自分のAmazonアカウントに登録されている全てのデバイス(Kindle端末、Kindleアプリをインストールしたスマホやタブレット)に自動で同期(配信)されます。
・読書:読みたいデバイスで本をダウンロードすれば、オフライン環境でも読書を楽しめます。
Kindleの何がそんなにいいの?
デメリットが注目される一方で、Kindleがこれほどまでに普及し、多くの人に支持されているのには、紙の本にはない強力なメリットがあるからです。
総務省の情報通信白書でも電子書籍市場の拡大が示されている通り、この利便性は多くの読書スタイルを変革しています。
最大の利点は、「物理的な場所を一切取らない」ことです。書斎がなくても、ワンルームの部屋でも、文字通り何千冊もの本を、スマートフォン1台や薄いKindle端末1台にすべて保存できます。
これにより、本棚のスペース不足に悩むことがなくなり、引越しや大掃除の際の手間も劇的に軽減されます。
また、「どこへでも大量の本を持ち運べる」利便性も大きいです。通勤電車の中、旅行先、ちょっとした待ち時間に、その日の気分で読みたい本を自由に選べます。
機能面では、専用端末の多くがIPX8等級の高い防水機能を備えている点も見逃せません。これにより、お風呂でのリラックスタイムや、万が一の水濡れが心配なプールサイドなど、紙の本ではためらわれる場所でも安心して読書を楽しめます。
さらに、電子書籍ならではの機能も充実しています。
Kindleの便利な機能
・文字の調整:文字のサイズや太さ、行間、フォント(明朝体、ゴシック体など)を自由に変更でき、視力や好みに合わせて最適化できます。
・ハイライトとメモ:重要な箇所にマーカーを引き(ハイライト)、メモを残すことができます。ハイライト箇所だけを後で一覧表示することも可能です。
・辞書・検索機能:読書中にわからない単語が出てきても、長押しするだけですぐに内蔵の辞書(国語・英和など)で意味を調べられます。特定のキーワードが本の中のどこに出てくるかを検索するのも簡単です。

検討材料となるメリットとデメリット
Kindleの利用を開始するかどうかは、これらのメリットと、これから解説するデメリットを天秤にかけ、自分の読書スタイルや価値観に合うかを判断することが重要です。
これまで見てきたように、Kindleには従来の読書体験を覆すほどの多くの利点がありますが、同時にデジタルサービス特有の無視できない欠点も存在します。
主なメリット
・物理的な保管場所が不要になる
・数百冊、数千冊の本を手軽に持ち運べる
・紙の書籍より安く購入できる場合がある
・文字の拡大やフォント変更が可能
・ハイライトや検索、辞書機能が便利
・防水端末ならお風呂でも読める
主なデメリット
・サービス終了時に読めなくなるリスクがある
・「所有」ではなく「利用権」の購入である
・アプリの操作性(特に本棚機能)が直感的でない
・中古として売却したり、他人に貸したりできない
・端末によっては目が疲れる場合がある
・パラパラと全体をめくる一覧性には劣る
例えば、「本棚に本が並んでいる背表紙を眺めるのが好き」という人や、「読み終わった本はすぐに売る」という人にとっては、Kindleのメリットはあまり響かないかもしれません。
これらの点を踏まえ、ご自身の読書スタイルに電子書籍が本当にフィットするかを考える必要があります。
kindleを買うか迷う?判断基準
「kindleを買うか迷う」という悩みの核心は、多くの場合「Kindle専用端末(Paperwhiteなど)を追加で購入すべきか」という悩みと同義です。
なぜなら、Kindleサービス自体は、専用端末がなくても手持ちのスマートフォンやタブレットに無料のKindleアプリをインストールすれば、すぐにでも利用開始できるからです。
専用端末を買うかどうかの判断基準は、「読書体験の質」と「追加コスト」のバランスをどう考えるかにかかっています。
読書専用端末(E Ink)の特徴
Kindle PaperwhiteやKindle Oasisといった専用端末は、「E Ink(電子ペーパー)」と呼ばれる特殊なディスプレイを採用しています。これは、紙にインクで印刷された文字に極めて近い表示を可能にする技術です。
液晶画面のように自ら強く発光(バックライト)するのではなく、周囲の光を反射して文字を見せるため、ブルーライトが少なく、長時間の読書でも目が疲れにくいとされています。
また、日光の当たる明るい屋外でも、紙の本と同じようにはっきりと文字が読めるのも大きな特徴です。
さらに、読書以外の機能(SNS、メール、ブラウザなど)が意図的に排除されているため、通知に邪魔されることなく読書に没頭できます。加えて、E Inkは電力消費が極めて少なく、一度のフル充電で数週間単位でバッテリーが持続する点も、スマホとの大きな違いです。
スマホ・タブレット(液晶)の特徴
すでにお持ちのスマートフォンやタブレットを利用するため、追加コストが一切かからないのが最大のメリットです。
また、高精細なカラー液晶を搭載しているため、雑誌や漫画のカラーページ、写真集などは、モノクロ表示の専用端末よりも美しく、快適に閲覧できます。
ただし、液晶画面は自ら光を放つため、長時間の読書では目の疲れを感じやすい人もいます。また、LINEの通知やニュース速報などで、せっかくの読書が中断されやすいという、集中力を削ぐデメリットもあります。
専用端末がおすすめな人
・小説やビジネス書など、活字中心の読書が多い人
・1日に1時間以上など、長時間の読書をする人
・長時間の読書で目の疲れを軽減したい人
・SNSなどの通知をシャットアウトし、読書に集中できる環境が欲しい人
・バッテリーの充電頻度を極力減らしたい人
kindle端末はいらないという意見も
「kindle端末 いらない」という意見も根強くあります。その主な理由は、「手持ちのスマートフォンやタブレットで十分代用できる」と多くの人が感じているからです。
特に、読書時間がそれほど長くない人や、読む本のジャンルが雑誌や漫画中心の人は、カラー表示ができず、活字に特化したモノクロの専用端末に数万円の追加投資をするメリットを感じにくいでしょう。
E Ink端末は活字の読みやすさでは圧倒的ですが、ページの切り替え速度(応答速度)が液晶に比べてワンテンポ遅れるため、この独特の「もっさり感」が肌に合わず、テンポよく読みたい人には不向きな側面もあります。
また、ただでさえスマホやモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンなど持ち物が多い現代において、「読書のためだけ」に新たなデバイスを持ち歩くことを純粋に面倒だと感じる人も少なくありません。
「読みたい」と思った瞬間に、ポケットからスマホを取り出してすぐに読める手軽さは、専用端末の優れた読書体験を上回る魅力となる場合があり、これが「端末はいらない」という結論に至る大きな理由となっています。
利用者が語るkindleのデメリットの詳細
ポイント
- kindleアプリはゴミと言われる理由
- kindleは使いにくくなったとの声
- Kindleは目が疲れる?端末の特徴
- サービス終了の懸念について
- Kindleで購入した本はずっと読める?
- 総括:kindleのデメリットとの付き合い方
kindleアプリはゴミと言われる理由
「kindleアプリはゴミ」という非常に厳しいインターネット上の評価は、特定の機能不全や不便さに起因しています。特に多くのユーザーが共通して指摘するのが、「アプリ内から直接Kindle本を購入できない」という致命的な仕様です。
これは、特にiPhoneやiPad(iOS)ユーザーに顕著な問題です。Appleはアプリ内でのデジタルコンテンツ販売に対し約30%の手数料を課しており、Amazonがこの手数料の支払いを回避するため、意図的にアプリ内からの購入機能を削除しているとされています。
そのため、ユーザーは読みたい本をアプリで見つけても、一度Safariなどのブラウザを立ち上げ、Amazonのウェブサイトで検索・決済し、それからアプリに戻ってダウンロードする、という非常に煩雑なステップを踏む必要があります。
この「ワンストップで完結しない」手間が、ユーザー体験を著しく損ねているのです。
さらに、購入した本を管理する「本棚(ライブラリ)機能」の根本的な使いにくさも、大きな不満点として挙げられます。
蔵書が数十冊程度なら問題ありませんが、数百冊、数千冊と増えてくると、ライブラリは混沌とします。読みたい本を探し出すのが困難になり、多くのユーザーがストレスを感じています。
・シリーズものの漫画や小説が巻数順に自動で並ばないことがある。
・「小説」「ビジネス書」「漫画」といったジャンルごとに自動で分類する機能が弱い。
・「コレクション」という名のフォルダ分け機能は存在するが、手動での登録が基本で操作が煩雑なため、蔵書が増えるほど管理が破綻しやすい。
これらの理由から、特に多くの本を管理したいヘビーユーザーほど、「アプリが使い物にならない」という厳しい評価を下す傾向にあります。
kindleは使いにくくなったとの声
長年にわたりKindleサービスを利用してきた既存ユーザーからは、「最近のKindleは使いにくくなった」という声が聞かれることもあります。
この不満は、アプリや専用端末のファームウェアがアップデートされることによるUI(ユーザーインターフェース)の変更が、従来の操作感と大きく変わってしまったことに起因する場合が多いです。
開発者側は「改善」のつもりで変更を加えても、長年慣れ親しんだ操作方法が変わってしまうと、ユーザーにとっては明らかな「改悪」と感じられます。
例えば、以下のような変更点が挙げられます。
- ホーム画面のレイアウトが大幅に変更され、自分のライブラリ(読みたい本)にたどり着くまでのタップ数が増えた。
- 「あなたへのおすすめ」といったレコメンド機能が前面に出過ぎて、自分の蔵書リストが見づらくなった。
- ライブラリの表示方法(リスト表示/グリッド表示)やソート(並び替え)の仕様が変更され、自分の使い方に合わなくなった。
機能自体は増えていても、シンプルに「自分の本棚から本を読む」という動線を邪魔されていると感じると、結果として「使いにくくなった」という評価につながってしまうのです。
Kindleは目が疲れる?端末の特徴
「Kindleは目が疲れる?」という疑問は、使用するデバイス(端末)によって、その答えが180度変わります。
前述の通り、Kindle Paperwhiteなどの専用端末は、紙と同様に「反射光」で文字を読む「E Ink」技術を採用しています。
画面自体が強く光るのではなく、内蔵されたフロントライトが画面を「照らす」仕組み(間接照明に近い)のため、目への刺激が少なく、疲れにくいのが最大の特徴です。紙の読書体験に限りなく近いと言えます。
一方で、スマートフォンやFireタブレットは、液晶ディスプレイ(LCDやOLED)を使用しています。これらは画面自体が「自ら光を放つ(バックライト)」仕組みであり、光(特にブルーライト)を長時間にわたって至近距離から見続けることになります。
厚生労働省も「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の中で、ディスプレイの輝度や照明とのバランスについて言及しており、不適切な環境での長時間の画面注視は、一般的に目の疲れや乾燥(いわゆるVDT症候群)の原因となり得ます。

サービス終了の懸念について
Kindleを利用する上で、最も本質的かつ重大なデメリットが「サービス終了の懸念」です。これは、デジタルコンテンツ全般に共通する根本的なリスクでもあります。
紙の本は一度購入すれば、それはあなたの「所有物」です。物理的に破損・紛失しない限り、誰にも奪われることなく永久にあなたの手元に残ります。
しかし、Kindleで購入した電子書籍は、法的には本そのものを「所有」しているわけではありません。ユーザーが購入しているのは、「Amazonのプラットフォーム上で、購入したコンテンツを閲覧し続ける権利(ライセンス)」に過ぎません。
もしAmazonがKindleサービスを終了したら?
万が一、将来的にAmazonが経営方針を変更し、Kindle事業から撤退してサービスを完全に終了した場合、理論上はライセンスの基盤であるプラットフォーム自体が失われます。その結果、購入時に支払った金額に関わらず、ライブラリにあるすべての電子書籍データにアクセスできなくなり、読めなくなるリスクがあります。
もちろん、現在世界的な巨大企業であるAmazonが、中核事業の一つであるKindleサービスを突然終了させる可能性は極めて低いと考えられます。
しかし、他の企業では実際に電子書籍サービスが終了し、ユーザーが購入したコンテンツを失った(またはポイント返還などで対応された)前例も存在します。
物理的な「モノ」として所有できない点は、電子書籍の根本的なデメリットとして明確に理解しておく必要があります。
Kindleで購入した本はずっと読める?
前述の「サービス終了リスク」と密接に関連しますが、ユーザーがより現実的に直面しうる問題が「アカウントの停止(凍結)」のリスクです。
Kindleで購入したすべての本は、あなたのAmazonアカウントに強力に紐付いています。
もし、何らかの理由(例えば、Amazonの利用規約に違反したと判断された、クレジットカードの不正利用が疑われた、アカウントが第三者に乗っ取られたなど)によって、あなたのAmazonアカウントが凍結または停止された場合、そのアカウントに紐付く購入済みのKindleライブラリ全体に、即座にアクセスできなくなる可能性があります。
紙の本であれば、Amazonのアカウントがどうなろうと、あなたの家の本棚にある本が消えることはありません。
しかし電子書籍は、プラットフォーム側の都合や、アカウントのセキュリティトラブルによって、過去に対価を支払ってきた大切な資産(蔵書)を一瞬で失うリスクをゼロにはできません。
したがって、「Kindleで購入した本はずっと読める?」という問いに対しての厳密な答えは、「Amazonのサービスが健全に継続し、かつあなたのアカウントが有効である限りにおいて読める」という条件付きのものになります。
総括:kindleのデメリットとの付き合い方
Kindleには、これまでに見てきたように、従来の読書体験を根底から変える利便性がある一方で、デジタルサービス特有の無視できないデメリットやリスクが存在します。
しかし、それらのデメリットを事前に理解し、メリットと天秤にかけることで、Kindleはあなたの読書生活を非常に豊かにする便利なツールとなり得ます。最後に、この記事の要点をまとめます。
ポイント
- KindleはAmazonの電子書籍サービス
- 料金は単品購入と読み放題(Unlimited, Prime Reading)がある
- メリットは場所を取らず、安価に購入できる機会があること
- 文字サイズ変更やハイライト機能も便利
- デメリットはサービス終了やアカウント停止のリスク
- 購入は「所有権」ではなく「利用権」である
- スマホアプリは目が疲れやすく、アプリ内から購入できない不便さがある
- 本棚機能が使いにくく、蔵書管理が難しいという声もある
- 「kindle端末 いらない」派はスマホの手軽さやカラー表示を重視する
- 「kindle 買うか迷う」場合は活字中心か雑誌中心かで判断する
- 専用端末(E Ink)は目が疲れにくく読書に集中できる
- 「Kindleは目が疲れる?」はスマホ利用の場合に多い悩み
- 「kindle 使いにくくなった」はUI変更への不慣れが原因の場合もある
- デメリットを理解した上で、便利さを享受するのが賢い使い方
- すべての本を電子化せず、紙と使い分けるのも一つの方法
※クリックすると公式サイトに飛びます。
期間内に解約すると料金はかかりません